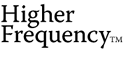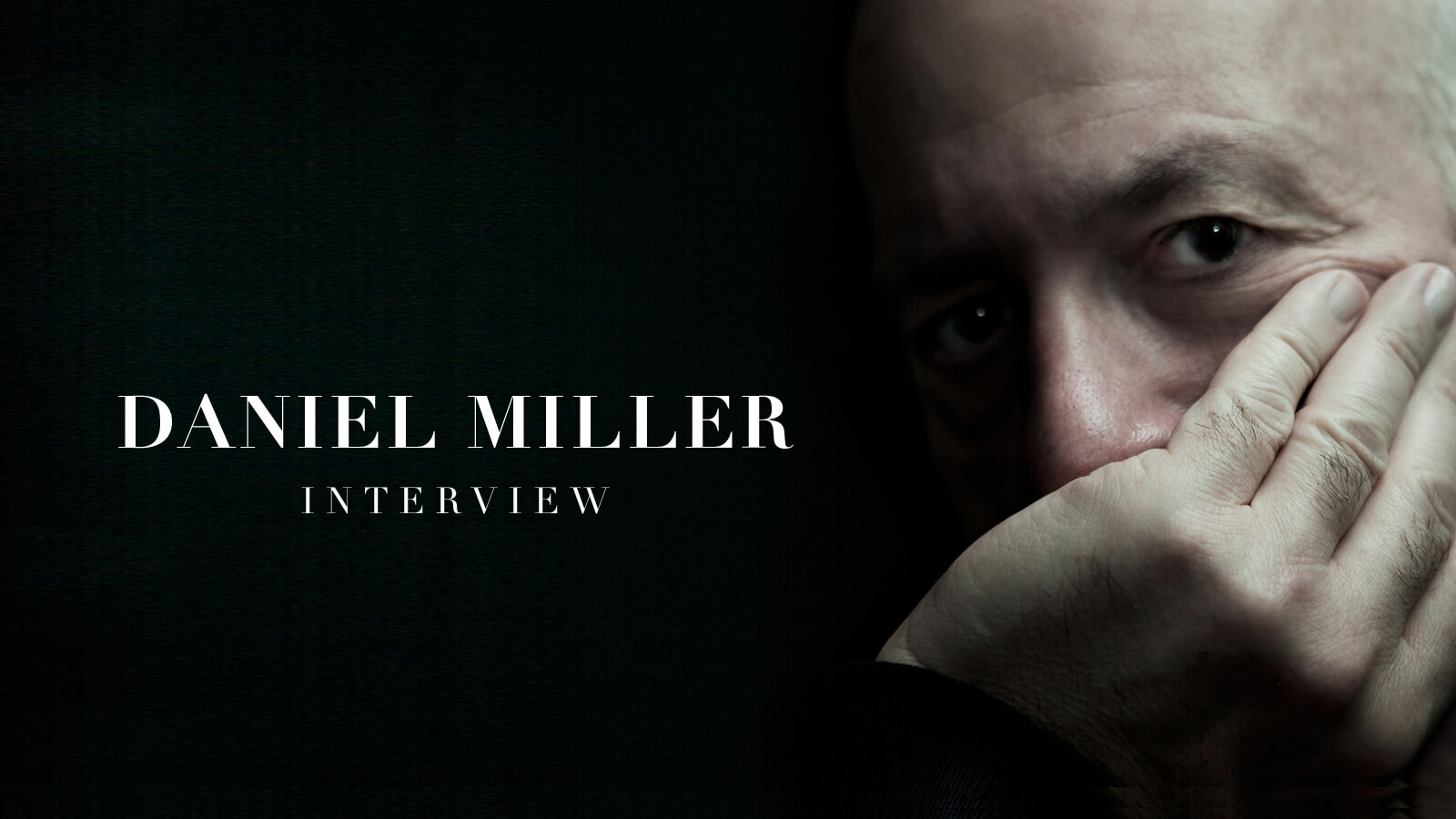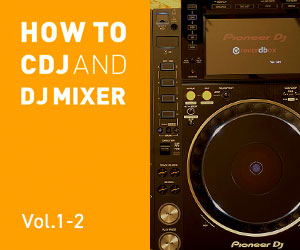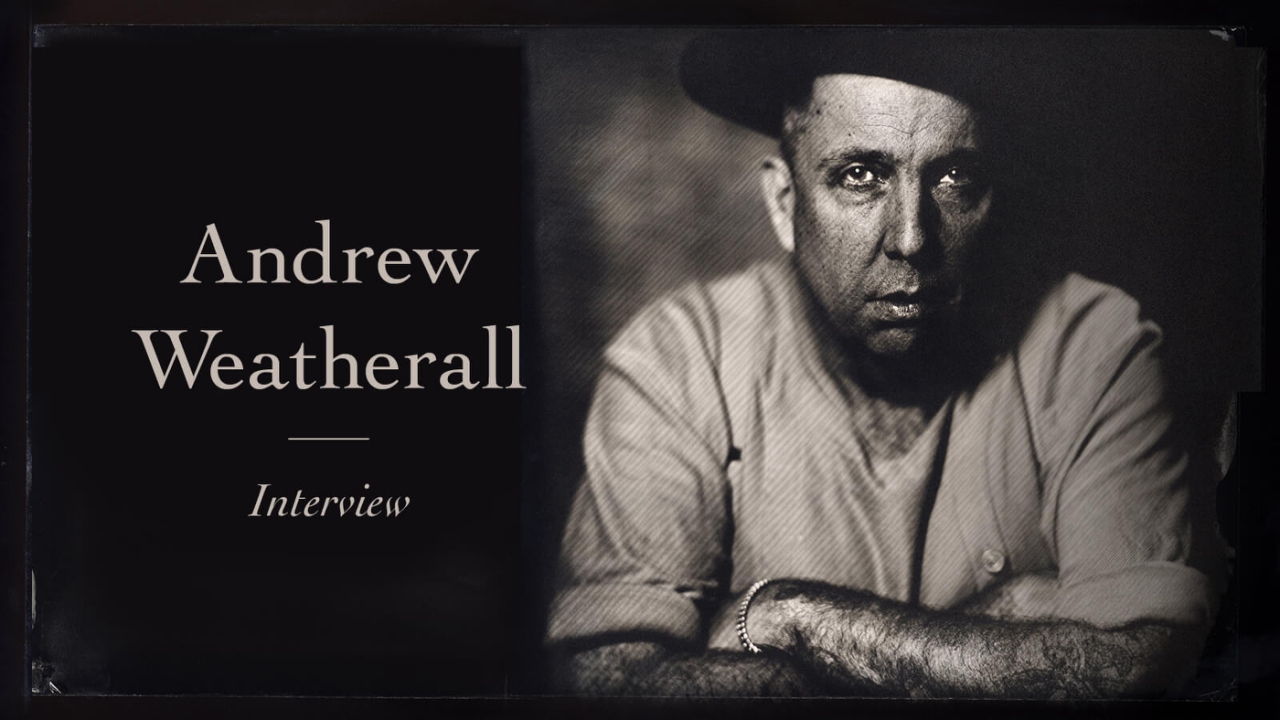INTERVIEW
Daniel Miller
Text & Interview : Hiromi MatsubaraTranslate : 光山征児Special Thanks : Night Aquarium, HITOMI Productions, Inc. & Traffic
2016.9.12
ゴッドファーザーのいまも変わらぬ情熱
初めまして。僕は22歳の、東京で活動している日本人のライターです。1994年に生まれて、10代の前半頃から、ロックからエレクトロニックミュージックまで様々な音楽を追い続けてきた僕にとっては、あなたは遥かに偉大な存在です。今回は、いまあなたは何を考えながら昨今の音楽シーンと接しているのか、ということを伺いたいと思い、いくつかの質問を考えさせていただきました。 今回、Daniel Millerに送った質問表は上記のようなメッセージから始まる。僕は、メールインタヴューをする際に送る質問表の冒頭に自己紹介以外のメッセージやを付けることはほとんどの場合しないが、なぜか今回は少し特別に感じていたのか、自然と手が動いてしまった。 なぜ〈Mute〉最盛期に直面していない世代の僕にとってもDaniel Millerが偉大な存在かというと、近現代の音楽史及び音楽文化を遡っていくと、必ずと言っていいほど〈Mute〉の膨大なカタログに突き当たるからだ。これについては、〈Mute〉が35年を迎えた際にWeb版『ele-king』で行われたDaniel Millerのインタヴューの冒頭で、野田努氏が最も適切だと思える一文を残している。 「電子音楽好きで〈Mute〉を知らない人間はまずいないでしょう。もしいたら、それはブラジル代表の試合を見たことがないのにサッカー観戦が好きだとぬかすようなもの」だと。 もう少し僕なりに掘り下げてみると、Daniel Millerと〈Mu ... READ MOREINTERVIEW
瀧見憲司
Text, Interview & Photo : Hiromi MatsubaraSpecial thanks : HITOMI Productions, Inc.
2016.9.1
パーティーの内側と外側で
やっぱり正直なところ、シーンは現場が突き動かしていると信じたい。現場で何かしらに揺さぶられて熱くなった人が動かしていると信じたい。音楽でも、クラブでも、アートやファッションでも、社会や経済でも、もう何でも。膨張するヴァーチャルだって結局はリアルな現場に流れ着く。そもそもリアルがあってこそ生まれたヴァーチャルだから、双方の地面は無意識に繋がっている。書は持たずとも、スマートフォンを手に、そしてMacBookを背負って町に出よう。 この東京、もとい日本に、特異な速度で流れている時間に僕はほとほと鬱屈する。24時間の中で、あるところは急速に動き、あるところは遅く流れる。鳴り続いている音楽は最新で面白いのに、フロアは一向に埋まらない。東京の辺境めいたディープスポットほど世界時間の感覚に敏感で、リアルタイムに欧米シーンを揺るがしている海外アーティストたちがやってくる。Instagramで見た動画やBoiler Roomのライヴストリーミングで見た景色と何かが違う。何かが遅く……何かがズレている。 瀧見憲司は、2016年9月3日(土)から始める20年ぶりのレジデントパーティー『OwK』から、東京のクラブシーンに生じたタイムラグとその因子にアプローチする。氏はローンチに際して「過去にも未来にも、水平方向にも垂直方向にも開かれた音楽が渦巻く、世代やテイストを超えて繋ぐユートピアでもありディストピアでもあるリアルなクラブパーティーにしたい」と言う。『OwK』の全てが詰まった内側 ... READ MOREINTERVIEW
Andrew James Gustav
Author : Philip Kearny (XLR8R)Photo : Carrie TangJapanese text : Hiromi Matsubara
2016.6.16
Andrew James GustavとGwenan。もしこの2人を知っているなら、あなたは相当なコアリスナーだろう。シーンの現状を見ると、プロデュースにせよDJミックスにせよ、一切リリースを持たずに活動をしているDJの情報はなかなか日本に伝わってこない。これだけワールドワイド、インターネット、SNS云々……と言っているにも関わらずだ。まして、2人のようにFacebookやTwitterのページを持っていない(あるのはSoundCloudページのみ)となると、もはや日本のシーンがどうこうは関係なく、2人が拠点とするロンドンのシーンを除く世界中の誰もが2人にアクセスする方法を限られている。しかし今、Andrew James GustavとGwenanはブッキングとトピックを増やし、いくつものウェブマガジンとラジオにDJミックスとポッドキャストを提供している。今回はその中から、『XLR8R』にポッドキャストを提供した際に行われたAndrew James Gustavのインタヴューの和訳版を特別にご紹介させていただく機会をいただくことができた。現代的なセルフプロモーション環境を持たず、ローカルなコミュニティーからグローバルなシーンへ躍り出しているAndrew James GustavとGwenanの現状は、わかりやすいぐらいにうなぎ登りだ。とはいえ、多くの出来事はあるひとつの側面と指標に過ぎないし、2人が飛躍している理由やプレイの良し悪しは、一概にはオンラインに転がっている情報だけでは ... READ MORE
タイムレスな表現を求める精神
お帰り! 完成おめでとう! 『Congrats』というタイトルにはその完成までの年月の重みが含まれているのだろう。2015年の12月、6年の沈黙を破り突如カムバックの予告ビデオを公開したHoly Fuck。猫の置物を次々と爆発させるその映像は、かつて“Red Lights”のMVでライヴをしていたキュートな猫たちを自らに置き換えて、過去のイメージをぶっ飛ばすかのような衝撃的な映像だった。そして、5月についにリリースされた最新作『Congrats』は予告通り、いや期待をゆうに越える荒々さと繊細さを兼ね備えた作品に仕上がっている。 無機質的で記号的なアルバムのアートワークとは裏腹に、アルバムに収録されている楽曲はアヴァンギャルドでいくつもの原色がカラフルな渦を巻いている。ますます破壊的になった人力インストゥルメンタル・サウンドは、聴いているとトランス状態になりそうだ。まさしくMVで表現されているような暴力的なサウンドの“Tom Tom”で幕を開けたかと思えば、“Xed Eyes”では反響の連鎖でレイヴィーな側面を見せ、続く“Neon Dad”はゆったりとしたテンポのエモーショナルなロックナンバーだったり、ラストスパートの“Acidic”では2014年に解散したThe Raptureの魂を継承したようなフロアライクなパンクイズムを兼ね備えていたりと、1枚のアルバムの中で彼らが大胆に「実験」をしている様子が伺える。 流行になびかず、時代に抗うかのように、独自のDIY精神を掲げて ... READ MOREINTERVIEW
Mumdance
Text, Interview & Photo : Hiromi MatsubaraInterpreter : Aoi KuriharaSpecial thanks : Fumie Kamba (DBS)
2016.5.20
無重力のレイヴ
2015年、Mumdanceこと、Jack Adamsは目覚ましい活躍を見せた。〈XL Recordings〉と契約しEP『1 Sec』をリリース、〈Fabric〉のライヴミックスシリーズのコンパイルを担当、そして相棒Logosとのアルバムリリース、加えて4枚の12インチのリリース……と、2013年に〈Tectonic〉からシングルをリリースして以来、年々高まっていたあらゆる期待に、量においても、質においても、見事に応えた1年となった。 2014年11月の『Red Bull Music Academy Tokyo』で来日していた際に彼にインタヴューをして以来、約1年半振りに再会して驚いたのは、Mumdanceの顔つきがかなり変わっていたこと。アカデミーで野心たっぷりな表情で〈Different Circles〉のことや、2015年の展望を語っていた時からは良い意味で若さが少し無くなったが、その代わりに大幅に増したプロデューサーとして貫禄は、多忙な1年が彼にとっていかに重要であったかをひしひしと感じさせる。 そして今回、その多忙な近況のあらゆる詳細に迫るのは、『Red Bull Music Academy Tokyo』でMumdanceと同じクラスで2週間を過ごした、梅谷裕貴ことAlbino Sound。久しぶりの再会を果たした2人は、Mumdanceの音楽性である「ウェイトレス・サウンド」をはじめ、発展するエクスペリメンタルな音楽の核心を突いた音楽談義で大いに ... READ MOREINTERVIEW
HELM
Text & Interview : Hiromi MatsubaraInterpreter : Shimpei KaihoSpecial Thanks : DJ Soybeans
2016.4.27
説明できない感覚は混乱の音楽に
あぁ……動いてるなぁ……、と感じることも音楽を聴く上での快感のひとつだ。何が動いてるかと問われれば、第一にはリズムであったり、メロディーであったりが、「音楽が動いている」という感覚と理解を与えている。しかし、どうやらその快感の極みは、むしろフィールド・レコーディングの方に、そしてそれを基にしたミュジック・コンクレートやノイズやアンビエントのような非音楽的なサイドにあるようで、肉声と機械音が混在する都市の喧騒や、今にも崩れそうな薄っぺらなビル群の軋み、ザラつきのある薄汚れた空気、それらを目の前にして生きる人間の胸の奥で渦巻く何かを、音楽として体感し、聴覚が他の五感とリンクした実感を得ることこそが聴いている側としてはリアルであり、身体的な興奮度が高い。そういった都市的なフィールド・レコーディングと生楽器のサンプリングが、マシンの限界を侵食し始めた時に生じるノイズを、リズムやループなどの方法とバランスという理性によって「エレクトロニック・ミュージック」へと昇華させた、HELMの『Olympic Mess』は最高に気持ち良くなれるアルバムだ。送り出したのは〈PAN〉。Bill Kouligasは、HELMの音楽を電子音楽史に新たなシーンを加える重要なドキュメントとして提示している。 HELMの狂騒曲をライヴで体感する機会があるとしたら。2016年のゴールデンウィーク、そのチャンスは日本にやってくる。迷わずにお近くの会場へと動くことをお勧めしよう。その前に、HELMを主導するLu ... READ MOREINTERVIEW
Young Marco
Text & Interview : Hiromi MatsubaraTranslation & Special Thanks : Shuhei Tochiori (P-Vine)
2016.3.8