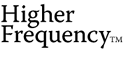INTERVIEW
Young Marco
Text & Interview : Hiromi MatsubaraTranslation & Special Thanks : Shuhei Tochiori (P-Vine)
2016.3.8
遠く、深く、生物学を辿る精神の探検
昨年開催された、『Rainbow Disco Club 2015』の3日目のこと。〈Rush Hour〉のオーナーであるAntalとレーベル看板アクトのSan Properと共に、変則B2Bを披露する「Rush Hour All Stars」の一員として登場したYoung Marcoは、BPM120とBPM60のトラックを表に裏にとひっくり返し続けながら、緩やかなムードを伊豆の大草原から空気中にまで染み込ませていた。どれぐらい緩かったかといえば、Young Marcoのプレイに合わせて、時折、San Properが「Marco、Marco、マ~ルコ〜……」とおふざけ的なMCをしたり、Antalの家族(特に妻)がステージ上でノリノリにダンスを披露したりして、笑い声と煽りの歓声が終始絶えなかった、という感じ。それも朝の9時から15時まで。途中、激しい通り雨に見舞われた時には、3人は少しテンポを上げて盛り上げてみたり、彼らの日本の大自然と寄り添うようなプレイは、環境すべてに相応しく、極上のひとときだった。さすがはオープンマインドに溢れる街、アムステルダムを代表する〈Rush Hour〉だ。
(そんな昨年のRDC最終日の「Rush Hour All Stars」によるロングセットは、180分にもわたる貴重なDJミックスのライヴレコーディングとしてRDCオフィシャルのSoundCloudにて公開されています!)
おそらくシーンの深層部にいた頃から、〈Rush Hour〉加入以降の今に至るまで、多様な文化が渦巻くアムステルダムで長らく活動してきたからという理由もあるのだろうが、それはともかくも、Young Marcoの音楽には底知れぬ奥深さがある。例えばそれは、彼がDJでプレイしているトラックや、リミックスを手掛けてきたジャンルの異様な幅広さにも言えるし、グラフィックデザイナーとして音楽に携わってきた一面にも言えるだろうが、何よりも、彼が自身の中に潜在している何かしらのストーリーに対して常に真摯に向き合いながら音楽を作っているということが大きいだろう。そうして、DJとしては10年以上のキャリア、また最初のオフィシャルリリースからは約6年を経て、2015年についに完成した1stアルバム『Biology』は、人間と自然の関係性にまで迫ったYoung Marcoのストーリーテリングと、稀有なプロダクションセンスを1ミリも違わずに伝えてくれる。メロディアスなシンセのレイヤーがゆっくりと立ち上げていく神秘的なサウンドスケープと、体内の奥から伝わるくぐもった鼓動のようなビートが相まった音楽は、最も人間的な側面から伝わり、ナチュラルなトリップを促す、全身に沁みわたるチルアウト。心が自然と開かれていくのだ。
以下のメールインタヴューの丁寧な受け応えからも、Young MarcoことMarco Sterkの魅力は伝わるが、彼の経歴や作品に関するもっと詳しい話は、僕が担当させていただいた『Biology』の日本盤に封入されているライナーノーツをご覧いただきたい。ちなみに、最初に海外でリリースされた『Biology』のヴァイナルはあっという間に売り切れて、今も割といい値段が付いているそうなので、インタヴューを読んで彼のことが気になった方はぜひ日本盤を。日本盤のみ収録のボーナストラック“Modular Birds”も極上の耳心地だ。

ーーあなたのDJやミックスを聴いていると、本当に様々なジャンルの音楽に精通しているんだなと感じるのですが、若い頃から色んなジャンルの音楽を聴いて、影響を受けてきたのですか? ダンスミュージックとはいつ頃どのように出会ったのですか?
Young Marco:僕は90年代にスケボーをやりながら育ちました。それで、その当時に見ていたスケボーのビデオのBGMとして流れていた音楽のジャンルが様々だったんです。ヒップホップ、パンク、ソウル、変なエレクトロニック、全部がそのビデオの中にありました。それが僕の音楽的嗜好の非常に大きな基礎になっています。またそれとは別に、僕は14~15歳の頃にプログラミングの仕事をやっていて、当時に初期の〈Warp〉のレコードをたくさん聴いていました。それが最初の「ダンス」ミュージックだったと思います。でも、そのレコードたちはダンスミュージックとしては作られてはいなかったんです。なので正直なところ、そこまでたくさんの「ダンス」ミュージックは聴いていませんでした。ちょっと退屈だったんです。いくつかのディスコのレコードだけは別でしたけどね。
ーーDJとトラックメイクはいつから始めたのですか? 始めたきっかけも教えてください。
Young Marco:高校生の時に、学校にあった古いMacやAtari、Commodore(コモドール)を寄付してもらったんです。真剣にではなかったんですが、その時から多少は音楽を作っていました。その後、18歳の時にアムステルダムに移って、自分でパーティーを始めて、DJもするようになったんです。そしてそのすぐ後に、僕にとって初めてのシンセサイザーである、poly800を買いました。poly800は今でもお気に入りの機材です。それからは全てのことが自然に進んでいきましたね。
ーーあなたのホームとも言える〈Rush Hour〉と、アムステルダムの音楽シーンとはどのようにして深く関わるようになっていったのですか?
Young Marco:アムステルダムは小さな街なので、外に出たら誰かと知り合いにならないことの方が難しいですよ。例えどんな音楽を作ったとしても、この街のシーンはとても小さいんです。それで、僕はたくさんの〈Rush Hour〉の人たちと意気投合しました。彼らとはお互いに手厚くサポートし合いながらここまで成長してきたと感じています。
ーー個人的に、アムステルダムのシーンの人々は誰もが実験的なチャレンジをすることに対して常にポジティヴに向き合っているような印象を持っていて、とても魅力的に感じています。あなたが思うアムステルダムのシーンの魅力的な部分はどういったところですか?
Young Marco:簡単に「アムステルダムのサウンド」と定義できる音楽はありませんが、アムステルダム的な精神はあると思います。それは姿勢としてはとてもオープンマインドです。例えば、〈Rush Hour〉、〈Red Light Records〉やRed Light Radio、Trouw(※東アムステルダムのヴェニュー)、『Dekmantel』、そして現在の学校といった全ての要素によって、とても健康的でオープンマインドなシーンがあるんです。最近ではたくさんのDJがアムステルダムに移住していますね。
ーーあなたはよくロングセットのDJをすることがあると思うのですが、DJプレイをする時のポリシーやルールはありますか?
Young Marco:ポリシーやルールはありません。自分にとっても、みんなにとっても、平等に良い時間を過ごせるようにしているだけです。僕はロングセットの方が好きです。長い方が良いですね。少なくてもひとつの物語を語るような感じが良いんです。最近では4時間のセットを「長い」と言うのはおかしなことですよね。4時間経ってからやっと始まるというのに。
ーーあなたの音楽活動歴は長いですが、2015年にリリースされた『Biology』が1stアルバムでした。(私のような)ファンはアルバムを待望していた反面で、あなたがアルバムというフォーマットでリリースしたことにも驚いていると思います。どうして今になってアルバムを作ろうと思ったのですか?
Young Marco:僕はこのアルバムが大好きです。自分のことをダンスミュージックのプロデューサーとは思っていませんし、アルバムというのはリスナーがストーリーを語るための余白と、もっと別の何かをするためのスペースを与えるものなんですよ。本当はクラシックのような1枚のアルバムを作りたいんです。(収録時間が)40分間だとアルバムの分量として相応しいとは言えないだろう、というレヴューをいくつか読みました。40分間だと彼らにとってはアルバムではなくEPとして映るんでしょうね。でもそれは当然ばかげたことで、70年代の多くのクラシックのアルバムはそのくらいの長さだったんですよ。
ーーなぜアルバムのタイトルを「Biology(=生物学)」にしたんですか? 言葉として、とても壮大な印象を受けます。何か生物学にまつわるエピソードがこのアルバムと関係しているのでしょうか?
Young Marco:Tom Tragoがよく私の音楽を「生物学の先生が作ったみたいだ」と冗談で言うんです。でも僕は、この言葉は意味としてもタイポグラフィーとしても美しいと思っています。この音楽はおそらく、人間性と、人間と自然の関係性について表しているので、理にかなっているんです。
ーー『Biology』に収録されているトラックの中には、「Trippy」や「Psychotic」といった人間のメンタル面にまつわる言葉が使われていますよね。そういった人間の精神は太古から長年にわたり、あらゆる場面において「自然」と深く関わってきました。アルバムを制作する際に、人間と自然の関係性について、もし何か特別なことを見出していたら教えてください。
Young Marco:私の作る全ての音楽は、長いライヴジャムからできていて、トラックたちは精神的な探検旅行の一部のであると切に思っています。ジャムをする時は、たまにネイチャードキュメンタリーをランダムに流して、時には生演奏でサウンドトラックをつけてみたり、時には自然の映像に創造性を掻き立てられたりしていますね。でも、いつも僕の心の中にある物語のナレーションのような感じでもあるんです。
ーーアルバムに続いて先日リリースされた、あなたのリミックスコレクションのタイトルが、『Sorry For The Late Reply(=返事が遅くなってごめんなさい)』なのはどうしてですか? とてもユニークなタイトルだと思いましたし、何か特別な理由が隠されているようにも感じました。
Young Marco:これらのリミックストラックたちに共通することって何だろうかと考えていて、唯一思いついたことがリリースが遅すぎたってことだったんです、 ははは(笑)。それぞれひとつずつメールで謝罪をして弁明をしました。残念なことに、いまではもうその言い訳を使うことはできなくなってしまいました。
ーーあなたがこれまでに手がけてきたリミックストラックの中でのベストはどれですか?
Young Marco:おそらく、Francis Bebeyのリミックスですね。関われてとても光栄だっただけでなく、かつてないチャレンジングなことでもあったからです。それでもかなり良く出来たと思っています。
ーーあなたはこれまでに数多くのリミックスを手掛けていますが、いつもどこから最初にリメイクしていくんですか?
Young Marco:いつもメロディーから手を加えていて、ビートからということはありませんね。
ーーリミックストラックを作る時と、オリジナルトラックを作る時の差は何ですか?
Young Marco:私にとってはどちらも同じです。どちらも同じやり方で作っているので、全く別物と考えてないんです。
ーーあなたが2015年に始めたレーベル〈Safe Trip〉の運営とキュレーションのコンセプトについても教えてください。
Young Marco:最初は僕のリミックスコンピレーションを出したくて始めただけだったんですが、同時に友人たちから届いた良い作品もいくつか持っていて、誰もどこからリリースするか決まっていなかったんですね。なので、これから様々なフォーマットでいろんな作品がもっとリリースされる予定です。
ーーでは最後に、今後の活動の予定を教えてください。
Young Marco:実現しないことが多いので、たくさんは計画は立てていません。でも常に何かしらの作業は進めています。唯一のプランは、自分が今やっていることをきちんとこなすことですね!
End of Interview

Young Marco
『Biology Deluxe Edition』
Release date: 2016/1/20
Label: ESP Institute / P-Vine
Cat no.: PCD-24459
Price: ¥2400 (+tax)
解説付 ※解説:松原裕海(HigherFrequncy)
Tracklist:
1. Biology Theme
2. Psychotic Particles
3. Sea World
4. Out Of Wind
5. Suzaku
6. Trippy Isolator
7. Can You Really Feel It?
8. Modular Birds – Bonus Track
More info: http://p-vine.jp/music/pcd-24459