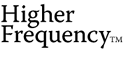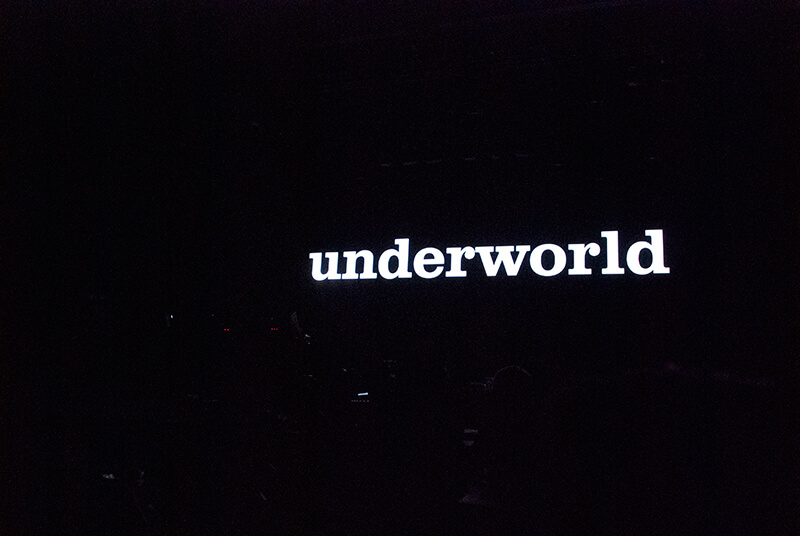Report
BERLIN FESTIVAL 2015
Text : Kana MiyazawaPhoto : Katsuhiko Sagai Thanks : Yuka Sagai
2015.6.30
テクノを生んだ街が10年の歴史とともにその力を世界に知らしめた ”BERLIN FESTIVAL”を追う
ヨーロッパを越え、日本も含む世界中から押し寄せた15000人以上のオーディエンスによって、10年の軌跡とともに大成功を収めたBERLIN FESTIVAL2015。記念すべき10周年となった今年は、UNDERWORLDをヘッドライナーに原点回帰ともいえるテクノ色の強いラインナップが存分に詰め込まれた3日間となった。
世界有数のクラブがいくつも存在し、毎週末、世界各地から訪れる人が後を絶たないパーティーシティーベルリンにおいて、”フェスティバル”というものが一体どんなものなのか正直想像が出来なかった。アンダーグラウンドであり続けたい街にとって、誰もが楽しめる言わば”お祭り”は必要ないのではないだろうか?そう感じていたからだ。
しかし、それは全くの反対であり、良い意味で裏切られたのがこのフェスだった。テクノを生んだ地であることを改めて世界へ知らしめるかのように、エレクトロもロックもハウスもベルリンのテリトリーであったかのような自信に満ちたパワーを見せつけてくれた。
Bjork、BLUR、PETSHOP BOYSといった豪華で異色のラインナップで開催した2013年を最後に、空港跡地のTempelhofからARENA BERLINへ会場を移し、今年は近隣のクラブやレストランを巻き込んだ大規模のものとなった。
初日となった金曜日の夜は、関係者受付から長蛇の列が出来、会場内はどこもパンパン状態。会場が広く、あちこちにステージが存在し、バーもトイレも多くほとんど並ばない。出店エリアやチルスペースも広々しており、いつでもゆったりくつろぐことが出来る。ヨーロッパのフェスやパーティーはこれが基本であり、さすがに驚かなくなっていたが、フード出店数が多く、ヴィーガン専用やワイン専門店などこだわった店が多く、どこで食べてもおいしかった。さらには、ミニサーカス場、無料で生花のリースが作れるブース、映画上映など音楽プログラム以外でも楽しむことが出来るコンテンツがとても充実していた。
一番驚き、そして残念だったのが、バーでキャッシュレスにするために導入していた最新システムだ。一見、画期的に思えるが、専用のブースでリストバンドに現金をチャージする必要があり、初日はどこよりも長蛇の列が出来ていた。さらには、デポジット制まで導入しており、購入時に渡されたチップとカップを一緒に戻してようやく1ユーロがバックされるという仕組み。もちろんキャッシュレスのため、1ユーロはリストバンドに戻される。残高が足りなければバーでは何も買えず、またチャージしに行かなくてはならず、とにかく面倒だった。残高を寄付することが出来たり、同系列のMeltで使用出来るなどいろいろ考えられたシステムではあったが、他のフェスでは是非とも導入しないで欲しい。
メインステージのARENA HALLEは幕張メッセを古びた巨大倉庫に変え、そこに最高級のサウンドシステムと一流のPAを仕込んだといった雰囲気。申し訳ないが音響の良さは比べ物にならない。天井からは白いボックス型のスピーカーがいくつも吊るされ、センターには360度スピーカー、ステージは背面に大きなスピーカーとスクリーンを背負い、会場のどこにいても安定した重低音が身体全体に響いてくる。不快な騒音、頭だけに響く耳触りな高音など一切なく、音にズブズブに埋もれてゆく心地良さだけが残った。
この環境で聴くJAMES BLAKEの歌声がこの世のものとは思えないほど美しかったのは言うまでもないだろう。他にも、世界初披露となったTigaのライブは背面の巨大なLEDライトの中で歌う姿がとても幻想的で、アイスランドが生んだ異色ユニットGus Gusのパフォーマンスはセクシーでエンターテイナーそのものだった。個人的には普段エレクトロを聴く機会があまりなく、詳しくもないのだが、アーティスト自身が芸術に携わっていたり、独自のビジュアルやパフォーマンスにこだわりを持っているため、不思議な魅力を放っていると感じる。
秒単位で変化し続けるVJ、七色のレーザーはデジタルで作られた巨大な万華鏡そのもので、その中で聴いたAMEのライブは予想に反してとてもロマンチックだった。
ロケーションが抜群にロマンチックだったのはシュプレー川に面したBADESCHIFFだ。砂浜のフロアー、ウッドデッキ、その先にはシュプレー川に浮かぶ美しいブルーのプール。このリゾーチのようなロケーションに、Tiefschwarz、ELLEN ALLIEN、PAN-POT、CARL CRAIGなど、このステージだけでベルリンを語れるほどの大御所テクノ勢が集結。
肌寒い日でもビーチステージには常に人集りは出来ており、ベルリンのテクノは砂浜にも合うことを証明していた。特にフロアーに向けた音を得意とするPAN-POTは笑顔のサービスとともに、ディープでありながら彩り豊かで気持ちよく踊らせてくれた。
会場内を移動中、斬新なヘアスタイルに真っ黒なファッションに身を包んだ集団が足早にどこかへ向かう。一番奥の森林広場のステージELEKTRONISCHE WIESEでプレイしていたRichie Hawtinのファンだった。緑に囲まれた中で、黒々したテクノに容赦ないスモークが焚かれ、その中で踊り狂う黒いミニマル集団は異様な空間を作り出していた。好きな音楽に合わせたファッションで個性を表現するのがヨーロッパのパーティーピープルの特徴でもある。そのためか踊る姿も皆自信ありげで堂々としている。
フェス自体は翌朝に音が止まるプログラムとなっていたが、それで終わるはずがない、終われるはずがないのがベルリンである。エントランスを出たすぐのところに位置するローカルクラブClub der Visionaere(以下、cdv)はフェス開催中24時間体制で開放されており、着地点を求めるWeekenderの受入先となっていた。
cdvについて少し説明しておくと、古びたボートハウスに、小さなDJブース、狭いフロアー、バーがあるだけの普段はレストラン・バーである。しかし、Ricardo Villalobosなど一流DJたちが挙ってプレイしており、アーティストからもベルリナーからもとても人気のあるベルリン屈指のクラブ。しかもエントランスは3〜5ユーロ(パーティーによって変動あり)人気のパーティー時には行列ができ、ドアポリシーもある。何より驚いたのはフェスのリストバンドをしているにも関わらず、中に入れない人がいたことだ。フェスが幕を閉じた途端、”ここからはオレたちの時間だ。相応しくないヤツは帰れ”と言わんばかりに”ベルリンの顔”に戻ったのだ。
そして、やはり最後には彼らの話でこのレポートを終えたい。90年代、世界中に衝撃が走った”Rez””Born Slippy”をこの世に誕生させたUNDERWORLDだ。2003年のElectraglide以来、12年振りだったが、まるで初めて見たかのような歓喜に満ち溢れた。彼らなしではこの世のエレクトロニック・ミュージックは語れない。真っ暗になったステージのスクリーンに映し出された楽曲1つ1つに涌き上がる大歓声、そこにはもう巨大な万華鏡も、他のステージも存在しなかった。”UNDERWORLD”ただ、それだけがそこに存在していたのだ。
こうして、とても大きな移動式サーカスのようなファンタジーなフェスティバルは幕を閉じた。クラブではスマートフォンのフラッシュが焚かれることはほとんどない。だからステージに向かって多くの人がカメラを手にしている光景を見た時に、一瞬どこに来たのか分からなくなった。もう随分とこの街のルールに馴染んでしまったようだ。
そして、またどこよりも早く長く、どこまでもディープなベルリンの週末がやってくる。