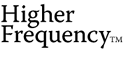INTERVIEW
Hudson Mohawke
Text : Hiromi Matsubara
2015.7.21
自由へと導くランタン、そしてやってくる新世界
「6年振りのアルバムですね」というのは、Hudson Mohawkeと最新作『Lantern』の話をする際には欠かせない話題ではあるが、彼が主にUSのヒップホップシーンなどを通じて常に面白いトピックを振りまいてきたのを見ていると、6年空くのも無理もないなと思う。ここ6年のヒップホップシーンは、90年代から衰え知らずの威勢でトップを張り続ける者もいれば、デビューする前からミックステープ(と『Pithchfork』のレヴュー)で注目を集めた後に1枚のアルバムでスターになってしまう者、はたまたメジャーレーベルからは何もリリースせずにスターになってしまった者もいるように、急激に役者揃いになった。Hudson Mohawkeはそういう変化の流れの中心地かつ最前線へと、自身の望み通り、年々接近していった。かつてのグラスゴーから現れた神童が、世界規模の革新者になるまでの6年というプロセスのポイントは、常に感心するしかないほどにワーカホリックなプロデューサーとして在り続けることだったのだ。Kanye Westの最高傑作『Yeezus』のクライマックスでもある“Blood On The Leaves”を後々共にプロデュースすることになる、Luniceと結成したユニットTNGHTとしてのリリースとツアーをきっかけに、Kanye Westの〈GOOD Music〉のプロデューサーチームの一員となり、DrakeやPusha-Tなど名立たるラッパーたちのトラック・プロデュースを連続してこなしていた。とはいえ、その間には2つのソロEPをリリースしていて、ここ3年は毎年ヴァレンタインデーには欠かさずに甘いソウルミュージックのミックスを届けてくれている。
『Lantern』は、そういったタームの最中にHudson Mohawkeの中に生まれた、彼なりのプロデューサーとしてのある1つの理想像を映し出している。“Warriors”や“Indian Steps”には、Hudson Mohawke自身がソウル・ミュージックをどのように咀嚼して吸収してきたのかがあり、フィーチャーしたアーティストとの関係には、Rick RubinやMike Deanといったベテラン・プロデューサーたちと共にスタジオワークをする中で何を学んだのかがある。ポップな様相と表裏一体の斬新性には、Travis ScottやMike Will Made Itといった同世代たちといかに刺激しあったのかを詰め込まれていて、その上で、いま自身がどういう音楽に惹かれていて、どういう感情を打ち明けたいのかを、1つのアルバムに、ストーリーとなっている。また、それは、このインタヴューのスピンオフとして『Spincoaster』に掲載した記事の冒頭でも述べた、「最高級のポップ・ミュージックは必然的に純度が高く、一体その純度が何を意味しているかというと、いかに自分自身に素直になれたか、あるいは、いかに自分の感覚を自由にすることができたか、だと思う」ということそのまま。そう、自分に素直に、表現に自由であること。さすればやがて、新しい世界(=“Brand New World”)はやってくる……。
Hudson Mohawkeと向かい合ってのインタヴューであれば、冗談めいた雰囲気もそれとなく含めて、「“Brand New World”のその先に広がっているものは何?」と訊いていたはず。そしたら彼は何と答えるだろう。プロデューサーHudson Mohawkeの新たな一面? 音楽への飽くなき探求?普遍的な明日が24時間毎に訪れるという最高の幸せ? とりあえずは、以下の彼の言葉を手掛かりに新しい世界を見据えていただきたい。

――『Butter』をリリースした時に「アルバムが出来上がるまでには1年だったけど、実質は3~4年ぐらいの作業が詰まっている」というようなことを仰っていましたが、比較的、あなたはアルバムをじっくりと時間をかけて作りたいタイプなのですか?
Hudson Mohawke:実際に6年もブレイクがあったとはいえ、意図的に6年空けたわけではないんだ。色んな人と出会って、本当、常に忙しく働いて過ごしていたよ。「1年があっという間に消えていた!」ってくらい。「僕は自分のソロ・レコードを作るので忙しくなるから、この仕事はやれない」っていう風になかなか言い出せない状況が続いてたんだよ(苦笑)。
――『Butter』をリリースした後からしばらくの間あなたが「一緒に仕事をしたい」と仰っていたKanye Westと関わるようになってから、あなたの状況は大きく変化したと思いますし、彼との出会いは今作に至るまでの6年という長い過程の中でも特に重要な出来事だったと思います。
Hudson Mohawke:そうだね。Kanye Westには、何年も自分からアプローチしようとし続けてきたんだけど、どうにもうまくいかなくて。で、それは〈Warp〉とのシチュエーションでも同じことだったんだ。っていうのも、どんなにデモを送ったって無理っていうのかさぁ……現実は誰も聴いちゃくれないから(苦笑)。アーティストにしても同じ話で、誰かのマネージャーや彼らのA&R担当者に自作曲のデモを送りたければ好きなだけ送れるけど、大抵の場合、彼らみたいな人たちの元には凄い数の音源が送りつけられてくるわけで、それら全てをいちいち聴いてる余裕は彼らにもない、と。だから基本的に、自分ではなく相手の方からアプローチしてくれる状況にならないと何も始まらないだろう、みたいなところがあるんだよ。ところがありがたいことに、彼らがロンドンにいた時に、たまたまラジオでかかっていた僕の曲を耳にしたみたいでね。で、彼らはその音源が何なのか探っていって、ラジオ局の関係者達、例えばBenji Bみたいな人々を通じて、僕のことを突き止めていったという。Benji Bは僕のトラックをよくかけてくれたから。それがまぁ、2、3年前の話で……2011年か2012年頃のことだったと思う。だから、向こうがたまたま僕の音楽をラジオで耳にしたのがきっかけで、僕にアプローチしてくれることになったっていう。本当、そもそもの始まりはそういうものだったんだよ。というわけで、本当に自分は運が良かったなと感じるんだ……向こうがなんともいいタイミングでラジオを聴いてくれたんだからね(笑)!
――ここ最近はKanyeを始めとするラッパーとの制作を数多く行っていましたが、今作にはラッパーをフィーチャーしていませんよね。ラッパーをフィーチャーしなかったことに関して何か意図はあったのでしょうか?
Hudson Mohawke:まぁ、その理由の一部としては、思うに大方の人々は……何と言うか、僕のことをただ単に「ラップのプロデューサーだ」って風に考えているんじゃないかと思ったからなんだ。僕は、自分にはそれ以外の面もあるってことをこの作品でちゃんと伝えたかったし、それにこのレコードを聴いてくれるようないまのリスナーには、僕が過去にやってきたこと、僕の初期のプロジェクトは一切知らないって人が多いだろうしね。僕の初期作品は、もちろんラップからの影響を受けた音楽ではあるけど、いわゆるれっきとしたとした「ラップ・レコード」でもなんでもないわけで。だからまぁ、今回ラッパーをフィーチャーしなかったのは、自分の音楽プロダクションにおける、ラップ以外の音楽へのアプローチの仕方を人々に見せたかったからで、今作はそういう一種の努力の賜物になったというかさ。僕たち(※「たち」は、S-TypesとNick Hookのこと)が去年やったプロジェクトのひとつに……僕がプロデュースを仕切ったあるプロジェクトで、実に36人のラッパーを使ったものがあって(※『The Rap Monument』のこと)。僕としては、「これはもういいや、ラップは充分」みたいに感じてた部分があったんだよね。だから今回のアルバムでは、人々にラップ•ミュージックとは別の自分の面を聴いてもらおうと思ったし、特に、僕の過去の作品にあんまり馴染みのない人たちと、僕のことをラップのプロダクションを通じてしか知らないような人たちに聴かせたいと思った。僕をあるひとつのスタイルだけで認識している人たちに向けて、今回の作品を通じて自分の持つ、もっと幅広いプロダクションへのアプローチの数々を紹介したかったんだ。
――でも、今後もラップのプロダクションは続けていきますよね?
Hudson Mohawke:うんうん、もちろん。今もまさに取り組んでいるところだしね! ただまぁ……今回のアルバムにおいては、この1枚に関しては、「ラップはあまり作品全体に合わないな」って、とにかく自分がそう感じただけのことで。僕はいま現在も沢山の様々なラップ・プロジェクトに関与しているところだけど、今回の自分のアルバムに関しては、特に「ラップ•ソングをやりたい」とは思わなかったんだ。
――フィーチャーをするシンガーはどのように決めたのでしょうか? また、共同の制作はどのように進めたのでしょうか?
Hudson Mohawke:相手によって求めるものが違ったってことはあるけど、総じて言えるのは……仮にもしも自分が、本当にビッグな人気アーティスト……例えば、過去2~3年で僕が一緒に仕事してきたような人たちをフィーチャーに引っ張ってこようとしたら、この作品が「僕自身のレコード」であるっていう点が損なわれかねないよな、って思ったんだ。っていうのも、ビッグアクトを使うと、聴く人々の話題も「誰それが参加してる」ってことに尽きてしまうわけでさ。だから、僕が自分のレコードに参加してもらいたい人を選んだ基準のひとつとして……もちろんアーティストとして僕が心からリスペクトしている人であり、その人のやる音楽を僕が大好きだって点はまずありきだったよ。ただそれと同時に、参加してもらったら「これが僕のレコードだ」という点が霞んでしまう、こっちの影が薄くなってしまうほどビッグな人をフィーチャーするわけにはいかないってのが基準の一部にはあったね。だから今作には、最近一緒に仕事をしていたような著名なラッパーが一切参加していないんだ。
――なるほど。中でも、IrfaneとAntony Hegartyをフィーチャーしたのは少し意外でした。彼らとの出会い、フィーチャーするに至った経緯を教えてください。
Hudson Mohawke:Irfaneは、僕が昔から彼の大ファンで、彼がBreakbotと作った曲も大好きでさ。かなり前から彼に連絡を取って、「一緒に曲を作りたい」と話していたんだ。インストのパートやビートは悲しい感じで、内容も別れの曲なんだけど、“Very First Breath”の仕上がりにはとても満足しているよ。で、Antonyについては……僕は本当「永遠にファンです!」ってくらい大好きなヴォーカリストだし、1枚目のアルバム(『Antony and the Johnsons』)の時から大ファンなんだ。これまでに何年も何年も手を伸ばし続けてきたんだけど、どうにもリーチできないままの存在でね。ところが突然、Antonyの方から「一緒に何かやらないか?」僕にアプローチしてきてくれて、実現したんだよ(照れ笑い)。
――Miguelはいままさに更なるスターダムに上り詰める途中ですし、Jhené Aikoは今後もっと活躍するであろう素晴らしいシンガーですよね。R. KellyやJohn Legendのプロデュースをした経験のあるあなたから見た、2人の魅力を教えてください。
Hudson Mohawke:Jhenéは、これまた長年大ファンだったシンガーなんだけど、彼女は「ヒットを狙って曲を作る」とか、そういうことを一切しない人だってところを僕は気に入ってる。クラブ・ヒットやスマッシュ・ヒットする音楽を作ろうとしてきたことが全然ないっていう。かつ、彼女のシンガーとしての美学には、全体的にとてもレイドバックしていてムーディーで、そしてダークな響きがある点も僕は好きだね。Miguelとは、実はかなり長いこと連絡を取り合ってきた仲なんだ。それこそ、彼がいまみたいに有名なビッグ・アクトになる前からだから、そうだなぁ……いわゆる「MySpace友達」だったって感じ……(苦笑)、かなり昔だろ? まぁ、そんな感じで前から何か一緒にやろうって話はしてきたんだけど、ああして彼は有名なシンガーになってしまって、僕としても「あー、こりゃもう無理だろうな」と思ってた。何か一緒にやりたくても、Miguelは大物になってしまったからもう難しいだろうって思ってたんだよね。でもダメ元で彼に聞いてみたら、答えは「イエス! ぜひやりたいよ」って感じで、彼が遥々ロンドンまで来てくれたんだ。彼は明らかに「スター」なはずなのに、傲慢なところは全く無いし、一緒に仕事していてとても気持ちの良い相手だったよ。
――長年の友人であるRuckazoidとのコラボレーションは念願だったのではないでしょうか?
Hudson Mohawke:うん、彼のことはターンテーブリスト時代から知っていてね。彼は本当にアメイジングなターンテーブリストなんだけど、そういうアーティストでありながらもテクニックだけが基本なのではなく、常に音楽性の感じられるプレイができるレアなアクトのひとりなんだよ。それで僕は彼のファンになったんだけど、彼がヴォーカルもこなす人だってことはこれまで知らなくてさ。だから彼が歌もやれると知った時は、「Ohhh, S**T!」みたいな感じだったよ(笑)!
――では、今作のアルバムタイトルの由来は何ですか?「Lantern」は暗い場所を照らす灯なので、 個人的にこの言葉からはポジティヴな印象を受けます。いまの音楽シーンを照らす灯になりたいというあなたの願望の現れでもあるのでしょうか?
Hudson Mohawke:いや、そういう意味ではないかな……。このアルバムは一種の「ファンタジーの世界における24時間」を描こうとしている作品だから、その時間の推移をガイドしてくれるものとして「Lantern(角灯)」が相応しいだろう、と。基本的にはそういうことなんだ。
――興味深いですね。「ファンタジーの世界における24時間」というのは具体的にはどういうストーリーなんでしょうか?
Hudson Mohawke:何と言うか、1日=24時間を通してランタンの動きを追って行く、みたいな。で、アルバムは夜明けや日の出を思わせるトラックから始まるし、それ以降も日中を思わせるポップ・ソングが続き、日が暮れてからのもう少しダークなトーンの曲、そして最後は夜になってクラブなモードになっていく……って風に、時間の流れを感じられるように全体をアレンジしてあるんだ。
――なるほど、だから“Lantern”で始まって、“Brand New World”で終わっているのですね。そのアルバムのストーリーの中でもかなり明るい印象を受けるオーケストラルなトラックたち、特に“Kettles”の様なトラックはHudMoの新たな一面と言えますし、新たな一面として捉えるリスナーが多いと思います。“Kettles”の制作の背景を教えてください。
Hudson Mohawke:まぁ……その新たな一面というのもまた、さっき話したことと関連してて、「〈Warp〉と契約していることの利点」から来ているんだろうね。メジャーレーベルでやる仕事とは違って、自分がどんなタイプの音楽にアプローチしてみたいかという点に関しては、実に様々な方向へ進んで行ける自由がある。だから、あの“Kettles”っていうピースについて言えば、あれは……もしかしたらメジャーレーベルから発表されるアルバムの中では成り立たない曲かもしれないね。自分でもそう思う。だけど、〈Warp〉みたいなレーベルとレコードを作る際に言えるのは、彼らが相手だったら実験してみる自由が許されるってことなんだ。実は、“Kettles”はここしばらく手元にあった曲で、ずっと発表したいと思っていたんだよね。ただ、自分でも「うーん、これは誰も聴きたがらない曲だろうな」と思ってて。いま人々が僕に対して求めているのは、ある特定のタイプの音楽に限られているし、あの曲は僕に期待される類いの音楽からは外れていると思うし、「人々に気に入られないだろう、誰にも理解してもらえないだろうな」って思ってたんだ。だからあれは……あの曲をアルバムに収録することに決めたのは、自分としてもちょっとしたリスクだった。というのも、あれは僕が自分の作曲スキルにチャレンジするために、音楽作りという意味で自分自身に挑戦すべく作ったような作品だったわけだけど、「聴いた人々が好むような曲か否か?」という点については、アルバムに収録すると決めるまで正直あまり考えたことがなかったからね。だからこれまでのところ、“Kettles”を聴いた人たちからの、この曲に対するフィードバックが本当に良くて僕としても嬉しいんだ。あの曲は確実に自分にとって新しい経験だったし、と同時に将来的に自分がもっと深く探究していくであろう領域だね。
――例えば、特徴的なホーン風の音とかは、今作だと“Scud Books”でも使われていますし、昨年リリースした“Chimes”でも似たような音のパーツが登場しています。あなたの中では、いま挙げたトラックたち、あるいは『Chimes EP』と『Lantern』の間にはどういった関係があるのでしょうか?
Hudson Mohawke:あぁ、うん、あれはただ……そうだね、さっき話した“Kettles”にも当てはまるんだけど、あれらは似た楽器を使って作った楽曲なんだ。で、それは純粋に自分にとって心に響くサウンドだから使ったってことであって、かつ……自分をエキサイトさせてくれるサウンドがああいうものだっていうことなんだよね。僕の作った曲には、ああいったオーケストラルな要素を持った曲がいくつかあって、それらはクラブ向けの曲ってこともあれば、純粋にオーケストラ調の曲もあって、あるいはヒップホップのビートを組み込んだ曲もある。だけど要は、全体としての響き、サウンドってことなんだよ。それが本当に僕の興味を掻き立ててくれるものかどうかなんだ。それに、いま僕達は今年の後半のどこかの時点で生のオーケストラを使ったライヴ・パフォーマンスをいくつかやるっていうアイデアを検討中でもあるんだ。
――それは素晴らしいですね。ちなみに、あなたはオーケストラのスコアやアレンジを学校などで正式に学んだ経験はあるんでしょうか?
Hudson Mohawke:いや、それはないよ。で、そういったことに対する僕の意見を言わせてもらうと……、いや、これはもちろん、非常に高度なクラシック音楽の訓練を受けてきた人たちに対する尊敬の念が欠如してるってことではないから誤解しないでほしいんだけど。っていうのも、僕だってそういうアカデミックな教育を受けられたら、さぞかし良いだろうなと思っているよ。ただ、と同時に自分が感じるのは……そうやって非常に高度なクラシック音楽の名演奏家みたいなものになるべくトレーニングを積む行為の中には、何と言うか、誰かから「これは正しい、これは間違っている」と正される側面も含まれていると思うんだよね。音楽の中では何が許容され、あるいは何が否定されるかを規定されてしまうというかさ。それに対して僕は、クラシックな音楽教育は一切経験してこなかった人間だし、とにかく……どんなタイプのサウンドを自分が求めているのか、どんなメロディーを使って音楽を作りたいのか、それは自分でもはっきり分かっているし、全て楽譜とかではなく、耳を通じて作業してるんだよね。で、ある意味自分はそのアプローチの方がむしろ好きだったりする。というのも、仮に自分が5~7年くらいかけて音楽をきちんと勉強して、本物の「クラシックで正統な音楽へのアプローチ」について学んだとしたら、逆に自分の音楽作りのアプローチの中に境界線や限界が生まれてしまうんじゃないか、っていう気がするんだよね。だから、アカデミックな枠の中では、人々から「これは間違っている」とか、「ここはこの時代の音楽の特徴を正確に表現していない」だのなんだの、色々と指摘されるわけで。だけど、僕にはそういった色んな決まり事が必ずしも関わってこないし、むしろそういうことをやりたいんだ。
――先ほど挙げたオーケストラルなトラックを、空気感はそのままに、よりエレクトロニックに作り上げたのが“Warriars”や“Indian Steps”だと思います。こんな言い方は変かもしれませんが……、あなたが本当に目指していたのはどちらかというと“Warriars”や“Indian Steps”の様な、じっくりと歌を聴き込むことができて、かつフロアでも確実に映える曲なのではないかと思ったのですが、あなた自身としてはいかがですか?
Hudson Mohawke:そうだね、さっきのアルバムのメインテーマと似たような回答になってしまうかもしれないけど……このアルバムのコンセプトは「クラブ・ソングだらけのアルバムにはしない」ということでもあるんだ。つまり、このアルバムはダイレクトにフロア映えすることや、クラブでプレイされることだけを狙ってるのではなくて……そういう要素を持った側面もあるアルバムだということだね。だから、いま言われたように、間違いなくクラブでプレイされて映えるような要素もあるけれど、それと同じくらいに、こう……「ヘッドフォンでじっくり聴き込みたい」っていう瞬間も備わったアルバムなんだ。例えば、明け方の5時頃に1人でひっそりと聴きたい感じの音楽でもあるっていう。だから、これは1枚の中にかなり幅広いジャンルが共存する作品だし……うん、さっきも話したラップのことと同様に、僕は「ただクラブ•ミュージックだけを作らなければいけない」というような「縛り」から離れたかったんだよ。
――今作はどんな機材を使って制作したのですか? また、6年の間に制作に使用する機材は変わりましたか?
Hudson Mohawke:前作『Butter』について言えば、あれはもっとコンピューターベースな作りのレコードだったね。それに対して今作では、僕はもうちょっとこう……直に手を使ってダイレクトに作るということをやってみたかったんだ。だから前作よりももっと生楽器を組み込んだし、ただコンピューターを使って様々なノイズを作り出す代わりに、ソフト・シンセではなく、本物のシンセを使った演奏ももっと多く組み込んでみた。このアルバムでは、確実にこれまで以上に多くの機材を使っているし、それにまた……ちょうどいまって、機材や楽器を山ほど所有したいと思わない、実際の楽器の購入に大金を投資したくない、っていう人たちが多い時代なんじゃないかと思ってもいて。というのも、ツアーで各地を旅して回らないといけない時とか、かさばる楽器たちを運搬するのは何かと不便だからね。それにもちろん、コンピューターだのラップトップだけで動き回るより、楽器を持って動くのは遥かに経費もかさむしね。だけど僕が今回ぜひやりたいと思ったのは、生楽器とコンピューターとを一体化させることだったし、かつ、ただアルバムを作るだけではなく、それらの要素をちゃんと設営したスタジオの環境において機能させたいということだったんだ。で、もしも自分がプライヴェート・スタジオをしっかり作ることなく、そういう部分を未処理のままにしていたら、おそらく今回のレコードでの様々なコラボレーション、例えばAntonyやMiguel、Jhené Aikoといった人々との共演は実現しなかったんじゃないかとも思うんだよね。っていうのも、もしもあれらのレコーディング環境が自分自身とラップトップだけで成り立っているような寂しいものだったら、きっと僕だって音楽作りを楽しめなかっただろうしね。だから、そうだなぁ……少なくとも6、7台ぐらいは色んなキーボードが置いてあって、それ以外にも様々な楽器や機材が用意されているような、そういうスタジオ環境の方がずっと楽しいだろうなっていう、いまの僕にはそういう感覚があるんだ。とにかく、そういう環境の方がもっとオーガニックで、かつ自分が音楽を作っていても楽しいと感じられるんじゃないか、っていう風に思えるんだよ。ひとりっきりで、コンピューターにコツコツと打ち込んでいくよりプロセスよりもね。
――以前、あなたは「(Kanye West絡みで)Rick Rubinと仕事をした経験から影響された」という旨の話をしていましたけど、彼はスタジオのヴァイブを重視していて、ミュージシャンたちの居心地が良い環境を作ろうとするプロデューサーという印象があります。
Hudson Mohawke:うん、その通りだね。
――そういう意味では、あなたはRickのスタジオでコツを吸収したのかもしれませんね。
Hudson Mohawke:ああ、そこは間違いなく彼から学んだことのひとつだったと思う。要するに、スタジオにおいて、「ある種の雰囲気」を生み出すのは非常に重要だ、ということだね。というのも、そうすることでレコーディングに参加した人たち全てを同じ気分へと持っていけるし……だから、例えばの話、5人くらいの人を寄せ集めてスタジオに引っ張ってきて、そこで彼らに何らかの音楽を作らせることはもちろん可能なんだけど、そのやり方が上手くいくとは限らないよね。ところが、まずそうやって集めてきた個性がバラバラな人たちの間に、ヴァイブや雰囲気を作り出すことに力を注いでみれば、そこで彼らはよりオープンになってくれるし、もっとこう……彼らはもっと好きに実験できる余地を感じ始めて、彼らならではの独自のプレイをやってくれるようになる。で、そうなった時こそ、他の人と仕事をする際に、彼らの内からベストな部分を引き出せる瞬間だろう、と僕は考えているんだ。ただ単に、スタジオに集まった連中に「これをやってください」、「あなたはここでこれをやって」って指図をするのではなく、実際にスタジオの中にある種の雰囲気を生み出せた時ってことだね。ただ「仕事」としてやるのは退屈なものだし、だからこそ、ある種の雰囲気をスタジオ空間に作り出そうとするんだ。
――そうやって、ミュージシャン同士の間にコネクションを生み出す、と。
Hudson Mohawke:その通り。
――そして素晴らしいアルバムが生まれる、と……。では最後に。7月に3年振りに来日することが決定しています。それも日本を代表するフェスティバル『FUJI ROCK FESTIVAL』への出演です。意気込みを教えてください。また、HudMoのライヴに備えて、私たちが準備すべきことがあったら教えてください!
Hudson Mohawke:ずっと「フジロックでプレイしたい!」って思ってきたからね。とても光栄に思っているよ! これまでのHudson Mohawkeのショウとはまったく違う経験になるはずだよ。楽しみにしてて欲しいな!
End of interview
リリース情報

Hudson Mohawke『LANTREN』
Release Date : 2015.06.16
Label : Warp Records / Beat Records
Cat No. : BRC-472
Price : ¥2,000 + 税
国内盤特典:ボーナストラック追加収録、初回生産盤CDのみシークレット・トラック収録
<Tracklist>
01. Lantern
02. Very First Breath (feat. Irfane)
03. Ryderz
04. Warriors (feat. Ruckazoid & Devaeux)
05. Kettles
06. Scud Books
07. Indian Steps (feat. Antony)
08. Lil Djembe
09. Deepspace (feat. Miguel)
10. Shadows
11. Resistance (feat. Jhené Aiko)
12. Portrait Of Luci
13. System
14. Brand New World
15. Chimes *Bonus Track for Japan
+初回生産盤のみシークレットトラック収録