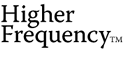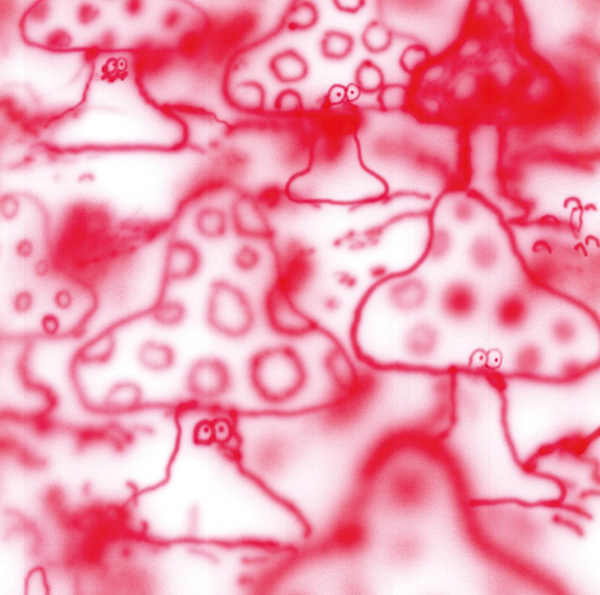INTERVIEW
Gonno
Text & Interview : Hiromi Matsubara
2015.7.27
時間と記憶のオリジナルサウンドトラック
一区切りというイメージがあるせいか、たまに俯瞰して見ると全長が短く見えてしまうことがあるけど、10年というのはやはり長い。10年も空くと、さすがにアルバムというフォーマットとの関係性や、その距離感も大きく空いているように見えてしまう。そう、イメージがかけ離れてしまうのだ。実際、Gonnoという人物を知ってからおそらくまだ5年も経っていない僕自身は、最新作『Remember The Life Is Beautiful』が「10年ぶりのアルバム」と言われるまで、前作のことはほとんどと言っていいほど意識をしていなかった。だから、今回のインタヴューで必要以上に「10年」や「アルバム」という言葉を使って問い続けているのは、Gonnoとアルバムの関係性をいまここで掴みたかったからだ。
『Remember The Life Is Beautiful』の音物語は、まず、2005年に『My Existence』をリリースしてからの時間と記憶が紡いでいく。プロデューサーとしては、ほぼ毎年国内外の人気レーベルから多くのDJたちに愛されるダンストラックをリリースして、DJとしては日本全国のパーティーやフェスティバル、さらにはヨーロッパを回り、数多の音の要素が激しくかつ綺麗に渦巻くプレイで人々を恍惚とさせてきた、音楽家としてのひととき。そしてそれを繋いでいく、本人しか知り得ない、多くの音楽、楽器、人々との出会いに揺さぶられてきた、ひととき。アルバムは、最初にも最後にも、あまりにも多くのことがありすぎたであろう激動の10年間を、いまや感慨深いひとときの連続たちとして抱えたGonnoの現在を映し出している。さらに本人曰く、10年というひとときの連続は、それ以前の時間と記憶をも喚起し、結びつけているという。
それに加え、このアルバムを素晴らしい作品だと断言したくなるのは、聴き手がアルバムの音物語へと入っていく隙間がしっかりと空いているからだ。これはGonnoの音楽活動のひとときが、不特定多数のあなたと音楽を通して向き合ってきたひとときでもあることを象徴的に示した部分で、GonnoがDJを続けてきた10年間で培ってきたテクニックに違いない。『Remember The Life Is Beautiful』は多くの人の時間と記憶にも重なっていく。僕と同世代の20代前半の1日、1年にも重なり、Gonnoと共に10年間クラブシーンを見つめて過ごしてきた人の記憶にも重なっていく。そしてどんなに最悪な日があったとしても、それは美しい人生のひとときだということを思い出させてくれる。

―― 10年ぶりのアルバムが完成して、もうすぐリリースされますが、いまの心境はいかがですか?
Gonno:改めて、アルバム出すのって凄い大変でした。10年ぶりなんですよねぇ……。単純に10曲完成させて出すっていう作業は本当大変だなぁというのが正直な感想です。
―― 今回はDisk Union特典のカセットテープ収録曲を合わせると12曲ですよね。アルバムの制作になると、Gonnoさんの中で「アルバムを作るぞ」って、モードは切り替わるんですか?
Gonno:全部が全部アルバムを作る目的で作られたというわけではないんですよ。だから、アルバムをトータルで聴き続けてもらうっていうストーリー性みたいなものを意識して、曲順は凄い考えましたね。で、その曲順に応じて、例えばアルバムの真ん中で間延びしてだらけたり、CDの尺に入りきらない長いものはあえてエディットして短くしました。
―― それで“Stop”と“Across The Sadness”は「アルバムヴァージョン」ということになってるんですね。この2曲は今年の2月に『The Muddler EP』としてリリースされてましたが、その時には既にアルバムの構想はあったんですか?
Gonno:一応、アルバムを作るのを念頭にシングルを出そうということを〈mule musiq〉さんとは話していたんですけど、全然作業が追いつかなくて。まずはとにかくシングルを出して、そこから作っていかなきゃという感じになったんで、『The Muddler EP』が出た時点では他の8曲はほぼできてなかったんです。
―― 急ピッチで完成に向かっていったんですね。
Gonno:そうですね。でもまぁ、断片的には作られていた曲はあったんですよ。例えば”Across The Sadness”は去年夏にはほぼ出来上がっていて、「rural」でも掛けたりして、徐々にブラッシュアップしていって。アルバムヴァージョンは尺を短くして、またギターを足してるんです。1曲目の“Hippies”も随分前にほぼ完成していて、2012年のUNITでのライヴの時(2012年3月31日開催の「MUSA」)にやったことがあったんですよ。
―― 披露はしていたけど、正規リリースはしていなかったんですね。
Gonno:そう。まだ完成形ではなかったんで。あと、“Already Almost”も2010年ぐらいにSoundCloudにこっそりアップしてた曲です。
―― ということは、仕上げるのは短期間で行われたけど、完成に向かうまでには長い時間がかかっていると。
Gonno:断片は作り貯めてあって……2月にシングルが出たところでスイッチを入れて、3月、4月でその断片を一気にまとめる作業に入っていったって感じですね。
―― 2005年の1stアルバム以降は「アルバムを出したいな」というような想いはあったんですか?
Gonno:10年ですもんね。もう、ずーっと出したいと思ってましたよ。
―― でもアルバムという形でのリリースからは離れてました、その理由は何ですか?
Gonno:いやもう単純にリリースしてくれそうなレーベルが無かったんですよ。
―― 〈International Feel〉とはアルバムの話にならなかったんですか?
Gonno:軽く話はありましたけど、2011年に『Acdise #2』をリリースしてから、2013年ぐらいまで〈International Feel〉にデモを全く送ってなかったんですよ。『Acdise #2』が幸運にもヒットしたけど、自分としては以後プレッシャーを感じていて、かといって『Acdise #2』のようなものを作りたいモードでもなくて。あと、その頃日本のレーベルからたくさんお声掛けをしていただいたので、2011年から2014年ぐらいまでは日本のダンスミュージックシーンが盛り上がると良いなと思って、主に国内のレーベルからのレコードやリミックスの依頼を引き受けてたんです。で、そろそろ『Acdise #2』のプレッシャーも解けていって、今年リリースされた”Obscurant”と“A Life With Clarinet” を、昨年の暮れに〈International Feel〉に送ったんです。
―― でも、2013年に〈Beat In Space〉からEPをリリースしていますよね。
Gonno:あー、そうですね。
―― あのリリースはどういう経緯で決まったんですか?
Gonno:『The Noughties』というEPのタイトル通り、あれは収録曲すべてゼロ年代につくられたもので、Tim Sweeneyが『Acdise #2』を気に入ってくれて(同EPのA面1曲目“Acdise #2”はFrancois Kevorkian、Laurent Garnier、James Holden、Todd Terjeら多くのDJにプレイされた)、2011年にTim Sweeneyが来日した時に、知り合いに「折角だから会ってみなよ」って言われて。Dommuneだったかな? その時に彼に未発表曲を渡したんですよ。そしたらそれを気に入ってくれて、だいぶ遅くなっちゃったけど、2013年にリリースされたっていう流れですね。確かそうだったと思う……2011年から2013年の頃が本当に忙しくて記憶が曖昧なんです。2013年にやったJeff Millsのリミックスとか個人的に傑作なんですが、もうどうやって作ったのか覚えてないです。
―― 初期は硬いテクノを作られてましたけど、〈International Feel〉からリリースした頃ぐらいからハウスになっていきますよね。当時心境の変化があったんですか?
Gonno:そうだな……でも意外と『Acdise #2』って、メロディックでバレアリックなイメージが先行しがちだけど、リズムや骨組みは〈Perc Trax〉から出してたものとそんなに変わらないんですよ。ああいうメロディーがあるから、バレアリックとかって言われるんでしょうけど……。何でだろうな……テクノが嫌いになったわけじゃないですし、そもそも「バレアリック」って語源は、「どんなものでも良ければプレイする」みたいな意味ですしね。
―― でも、もともとはハウスのDJだったんですよね。
Gonno:そうです、ハウスからDJカルチャーに入って。でも、そのうちハウスも「ハウスとはこうあるべき」みたいな様式美化してきちゃって。DJを始めた頃も「GonnoくんのDJ盛り上がるけど、NYっぽくないからなんか違うんだよね」と言われたりしました。僕はへそ曲りなんで、そういった変な本物志向が出てくると、途端につまらなくなっちゃうんですよね。で、他にもっと色んな音楽があるよって友達に教えてもらって、テクノとか、エレクトロニカ、ドイツのディープハウスとか、ミニマルとか、ちょうどAkufenが出てきた頃で、そういった当時新しく出てきたダンスミュージックを好きになっていきました。でもいま現在、テクノもそうなってきちゃってる感じがするんですよね。「ベルリンらしくないとダメ」とか。「Richie Hawtinっぽくない」とか「Ricardo Villalobosがプレイしてくれない」とか、はたまた「〈Ostgut Ton〉っぽくない」とか、僕はそういうのから逃げ続けたいんだと思います。ちなみに、〈Ostgut Ton〉のNick HoppnerやTama Sumoは顔見知りですけど、彼らってハウスとテクノどっちのセットをやってもDJが凄く良いんですよ。
―― Gonnoさんは、どちらかというと、ご自身の中で設定した満足のいく水準に達さないとリリースできないタイプなんですか?
Gonno:確かに凝り性だと思います。いままでのシングルもアルバムもそうなんですけど、マスタリングを1回でOK出せたことがないんですよ。レーベルには迷惑が掛かっちゃうんで申し訳ないんですけど。あと以前に依頼のあったリミックスも3ヶ月ぐらい待たせてしまったりとかありました。リリースされた後にも、プレイ用に自分でリマスタリングとかよくしますね。
―― じゃあDJではリマスター版をかけてるんですね(笑)。
Gonno:そうそう。まぁ所謂オタクです(笑)。
―― 好きだからこそ余計にってことですよね。
Gonno:そうですね。粗が気になっちゃうんで、ギリギリまで直したくなっちゃうんですよ。最近は大分ジャッジが早くなりましたが。
―― そういう凝り性な部分はアルバムをリリースする時も出てきますか? 例えば、今作は長い時間が詰まっているから特別な思い入れが出てきたりだとか、アルバムだとトラックの組み方がまた変化するから悩んでしまったりだとか。
Gonno:特段、アルバムを出すことに関しては12インチのEPとかと変わらないですけどね。でも個人的に、アルバムってダンスミュージックに限らずにとても沢山聴くから、やっぱりアルバムでしか聴けないストーリー性みたいなものは意識しました。全編がダンスミュージックのツールとかではなくて、例えばアルバムの中盤の流れで静かになっていって、また盛り上がっていく、っていう流れがしっかり組まれている感じで。
―― 確かに、今作にはかなりしっかりとしたストーリー性がありますよね。ハウストラックの後には、アンビエントやエレクトロニカっぽいテイストの曲がきて、っていう流れにメリハリがあったので1曲ずつがより印象的になるというか、凄い入ってき易かったです。
Gonno:ありがとうございます。でも自分ではわからないんですけどね。ベストを尽くしたつもりですけど、心配になっちゃいますよね。リリース後はいつもそうなんだけど。
―― これは『Remember The Life Is Beautiful』っていうアルバムタイトルからも思ったことなんですが、ストーリー性含め、今作にはこれまでGonnoさんに起こった色々な「記憶」が深く関わっているのかなと。
Gonno:あぁー。自分では気付かなかったけど……でもそうかもしれない。前作から10年空いて、その10年間の中で作られたものなので、必然的に自分の想いとか「人生の10年」みたいなものは、無意識に曲に刻まれているんでしょうね。ちょっと気恥ずかしいですね。
―― 大事なことだと思いますよ。例えばトラックタイトルだと“The Island I’ve Never Been”とか……、それこそ“The Worst Day Ever”とかは「そんなに最悪だったのか」と思いましたね。
Gonno:はははは(笑)。
―― でもそういう、ひとつひとつの記憶がトラックの元になっているのかなと思いました。
Gonno:そういった体験記みたいな部分はあるかもしれない。基本的に……「こういうスタイルで、こういうサウンドで作ろう」みたいな作り方をあまりしないで「こういう感情を音にできたらいいな」みたいなところから作り始めたりするので……、何だろう……横文字で言うと平たくなっちゃいますけど……そういうエモーショナルな部分から曲の着想を得ることは多いかもしれないですね。
―― 普段から音楽以外の物事を元にしてトラックを作ることの方が多いんですか?
Gonno:例えば本を読んだり、映画を観たりして、曲を思い浮かぶことは全くないですね。体験からの着想が多いのかな。些細なことでも体験から引き起こされる感情とかを、例えばDJをしていて音楽を沢山聴いているので、その自分が持ってる音楽のボキャブラリーから「あの音楽を聴いた時にこんな風に思った」っていうのがサッと出てきてるみたいな感じですかね。
―― なるほど。「記憶にサウンドトラックをつけてる」って感じですね。
Gonno:それはカッコイイ表現ですね(笑)。カッコイイ感じで言うとそうなのかもしれませんね。
―― Gonnoさんの中で呼び起こされてる感情や記憶っていうのは、10年の間に日本全国をDJして巡ったり、ヨーロッパでプレイしたりといったDJでの経験に基づくものの方が多いですか?
Gonno:必然的にそういう部分も含まれていると思うんですけど、もしかしたら、いま曲目を見ながら曲を思い出しながら思ったのは……アルバムのほとんどの曲でギターを弾いてるんですよ。ギターそんなに上手ではないんですけど、ロックとかギターの音楽を聴いてたのは主に10代の時なんですよね。なので、10代の時の記憶というか、そういうものを自分がいま作ってるダンスミュージックとかに喚起させたかったのかもしれないですね。……なんかカウンセリングみたいだなぁ(笑)。
―― すみません(笑)。
Gonno:いやいや。凄い面白いですね。自分では気付いてなかった。10代の時に聴いていたものと、いま自分がやっている音楽を上手くかけ合わせたかったのかもしれないですね。
―― 以前、GonnoさんにDJをする時のこだわりについて伺った時に、「テクノもハウスも一緒にかけたり、色んなジャンルをかけたりして幅を見せたい」と仰ってたと思うんですけど、今作はストーリー性も然ることながら、そういうDJの時のこだわりにも通じるようなジャンルの幅もしっかりと見せたアルバムになっていると思いまして。
Gonno:はい。
―― Gonnoさんのハウストラックのビート以外の部分や、今作でいうと“Already Almost”や“Beats In Your Mind”みたいなビートレスなトラックとかは、初期のFour TetやBibioのアンビエント、エレクトロニカ感と通じる部分があるなと思ったんですが、トラックを作る時はメロディーや和音の方が先に想い浮かぶんですか?
Gonno:場合によりますけど、リズムがあるものは、基本的にはリズムからできてますね。リズムがあるものって、やっぱりグルーヴが凄い重要だと思うので。そのリズムに合うようなメロディーや和音を付けていく流れですね。メロディーらしきものっていうのは、もう完全に手癖なんでしょうね。和声に関してそこまでボキャブラリーが無いので。ほぼ無意識に作ってますね。例えば、2曲目の“The Worst Day Ever”はシンセのリフはMoogのLittle Phattyを使ってますが、まず一番最初に変わったリズムを作ろうと思って、マイクの一部を指でボンッと叩いたものをキックにしたりしながら組み立てていきました。その後にメロディーを付けていって。やっぱりリズムから組み立てていく方が多いかも。
―― 逆なのかと思ってました。
Gonno:本当ですか。でも僕もいま気付きましたね。何でなんでしょうね。
―― 特に意識して組まれていた制作の流れではないんですね。
Gonno:そうですねー。全然意識してないなぁ。何ででしょうかね……リズムから作るのはやっぱりDJだからでしょうかね。
―― なるほど。でも今作はビートレスのトラックもいくつかあるじゃないですか。
Gonno:ビートレスなものに関して言えば、例えば“Already Almost”とかは、フィールドレコーディングしたものやギターをだらだらと弾いたものを下敷きにして、そこに和音を付けていって、さらにまたフレーズを足してという感じですね。
―― リズムを足そうと思ったりは特になく、このままの形で完成にしよう、という……。
Gonno:そうですね。これはもうこれで、リズムや打楽器はいらないかなって。DAWのグリッドを意識しないでつくったものなのでリズムは付けませんでした。
―― ということは、リズムを入れてないものは、リズムを入れないという想定で作っていくんですか?
Gonno:いや、これは結果的にです。仮に元がリズムのあるものでも、ドラム入れても面白くないでしょ、って思ったら外しますし。
―― 今作のリズムセクションだと……“Hippies”や“Revoked”のイントロに入ってるドラムは実際に叩いたものを使ってるんですか?
Gonno:これ実は全部ソフトウェアなんです。あるドラムのソフトウェアがあって、それが生ドラムに近い音になるんですよ。
―― 打音がひとつひとつ違いましたし、人力ハウスバンドみたいだなって思いました。
Gonno:打音の調整は自分で強弱を手動で打ち込んでいたり音程も変えたり、音色自体もかなり加工してるんですけど、ソフトウェアが凄い優秀で「ヒューマナイズ」っていう機能があってそれを少し多めにかけると人間味のあるズレや強弱がつくんですよ。それを使ってますね。
―― 録ったのかと思ってました。
Gonno:本当は録りたいんですけどね。実際に好きなドラマーがいて、森は生きている、っていうバンドの増村くんっていう方なんですけど、僕、彼のドラムが大好きで。
―― それで“ロンド”のリミックスをされてたんですか?
Gonno:いや、順番はその逆で、リミックスのお話がきてから森は生きているを知ったんです。リミックスを引き受ける前にまずライヴを観に行ってみようと思って、行ったら、バンドの演奏が素晴らしかったんですよ。メンバーの皆さん本当に演奏が上手なんですけど、特に増村君のドラムが素晴らしくて。
―― ホントに、凄い上手いですよね!
Gonno:本当は今回参加していただきたかったんですけど、アルバムの制作時間がなくて。ライヴで忙しいだろうと思って誘う気も引けてしまいまして。

―― 今作は“Green Days”にCrystalさんとInner Scienceさんが参加されてるから、実はもっと参加アーティストがいて、裏側でGonnoバンドが結成されてるのかと思ってました(笑)。
Gonno:はははは(笑)。自分の頭の中で、「バンドやりたいなぁ」なんていう構想はあったんですけどね。いつかやりたいですね。
―― CrystalさんとInner Scienceさんとの共作はどういう経緯で始まって、どういう進行だったんですか?
Gonno:去年のThe Fieldの来日公演(2014年1月17日)の時に3人で共演したんですね。その時に、3人で曲を作ってみようかっていう話になって。みんなの頭文字を取って「クリンゴン」っていう名前でやろうかっていう悪ノリで(笑)。でも3人で作ろうみたいな話はずっとしていたので、今回が良い機会だったので2人にお声掛けしました。Crystalくんとは別でいま1曲共作をつくってますけど、また3人でこれから一緒につくれたら良いですね。
―― 3人でスタジオに入っての作業はしたんですか?
Gonno:いや、完全にメールで素材を交換し合ってって感じですね。イントロで流れてるマレットっぽい音をInner Scienceが作って、それにCrystalくんが音を付けて、それに僕が音を付けてっていうのを2回転やって完成しました。
―― 2回転ってことは、比較的スピーディーに完成したんですね。
Gonno:そうですね。思ったほど時間はかからなかったですね。
―― 意思疎通の面は、ディスカッションとかしたんですか?
Gonno:いや、全然してなかったんです。不思議なことに、この3人って音楽のルーツが全然違って、Inner Scienceはヒップホップがルーツで、Crystalくんもまた僕と違った出自で……でも不思議なんですがお互いの音楽がよく合うというか。
―― 不思議ですよね。ソロと(((さらうんど)))ではまた違いますし、多彩ですよね。
Gonno:そうそう、実際にバンドもやってたり凄い色々なことをやってるから、僕ともまた違う。でもなぜか3人とも共通した音楽的要素がどこかあるみたいなんですよね。それに、元々僕はInner ScienceがやってるPortralっていうアンビエントとかを作ってる別名義のアルバムが大好きだったんです。そういった尊敬する2人との作業なので、フレーズができてくると、みんな「いいね、いいね」って感じですぐにできたんですよ。結果的にできた曲が、我々3人の共通する青い要素がかなり色濃く出たんで、こういうタイトルに……。
―― それで“Green Days”なんですか!(笑)
Gonno:そうなんですよ(笑)。10代の感じというか何か……郷愁というかね。中二病ともいうのかも。
―― ちなみに、その他のトラックタイトルやアルバムタイトルはどうやって決めていったんですか?
Gonno:実は『Remember The Life Is Beautiful』っていうタイトルも、リリース前のギリギリになって変えたもので。最初本当に決まんなくて。何にしたら良いのか悩んで、単純に「2」とかにしようと思ったんですよ。
―― セカンドアルバムだからですか。
Gonno:そうです。でもやっぱり味気ないと思って。いまのこのタイトルになったのは、随分前に、ある外国人の方のお宅にお邪魔して、僕が帰る時にその人が「じゃあね、またね」って言うのと一緒に「Remember the life is beautiful!」と言ったんですよ。Ray Hearnっていう方なんですけど、あれ以来お会いしていないですが、凄い良いフレーズだなってずっと思ってて、それを思い出してこのタイトルにしたんです。
―― 素敵なエピソードですね。作品にぴったりハマってますし。
Gonno:実は遺作でこのタイトルを付けようと思ってたんですけどね(笑)。もう早々につけちゃいました。
―― さらに制作環境について伺っていきたいんですが……、先ほども仰ってましたけど、今作はフィールドレコーディングも結構使われてるんですか?
Gonno:してますね。フィールドレコーディングもそうだけど、マイクで録ったものはかなりありますね。さっき言った、マイクを叩くとか、アコギをマイクで録ったりとかは沢山しました。あとiPhoneのマイクで言葉とか環境音を録音するのが結構好きで。近所で……あの……独り言を大きい声で言ってる人ってよく見かけるじゃないですか。そういう時に、iPhoneのアプリを開いてこっそり録ったりします。かっこいいなぁって思いながら。
―― 確かに良いですよね。言葉そのものに意味があるようで無いから、より音素材的というか。
Gonno:そうですね。録音って二度と同じものにならないものですし。自分では出せない、その環境や人でしか出せない音ですからね。とはいえ、フィールドレコーディングと言ってもその程度のもので、本格的なフィールドレコーディングにも興味は凄いあるんですけど、田んぼのカエルの鳴き声とかを高音質で録るっていうような機械を持ってるわけではないので。後々そういうこともやってみたいですね。スピーカーから環境音を流して、田んぼの中に居るような感覚を作るというか、他のスピーカーから音楽も流れてるんだけど、その場所を喚起させられる音も流れて、っていうアンビエントミュージックを作って欲しいみたいな話もいただいているので、やってみたいなと思ってるんですけどね。
―― 今作は、所謂ロウな感じやアナログ感が多く含まれていると思ったんですけど、アナログ機材は使いましたか?
Gonno:所々使いました。アシッドなベースラインは、AcidlabのBasslineっていうRolandのTB-303のクローンをほとんど使ってますね。“Hippies”とか、”Green Days”とか。それと、ほぼ全編でさっきも言ったMoogのLittle Phattyを使ってますね。“Beats In Your Mind”は、KORGのVolca Keysっていうアナログシンセだけで作ってますね。安いんですけど音が可愛らしくて良いんですよ。フレーズも内蔵シーケンサーを走らせて作りました。フィルターの効きも、とても人懐っこくて可愛らしいんです。

左上: KORG「Triton」/ Acidlab「Bassline」, Moog「Little Phatty」, KORG「Volca Keys」, MIDAS「Mixer」, Fostex「XR-7」, Acoustic Guitar / Electric Guita
―― 機材は、10年間で相当な量と回数変わりましたか?
Gonno:だいぶ変わりましたね。言ってしまえば10年前の『My Existense』は、KORG Triton以外、ほぼソフトウェアでつくってましたからね。今作でもTritonは変わらず使ってるんですけど、10年前はハードウェアはそれだけだったと思うので。それから考えると大分増えましたね。10年前のアルバムではギターも弾いてなかったですし。
―― 今作の制作セットアップになったのはいつ頃だったんですか?
Gonno:うーん、徐々に増えていった感じなんですが、アルバムを作り始める直前に、ライヴでしか使ってなかったMIDASのミキサーに全部セットアップして。例えば、サミングって言う方法なんですけど、あえてコンピューターの音をミキサー卓に通してからまた戻して、とかやりました。あとは、パートをカセットテープで録って、それを再生してまた入れていくっていうこともやってます。その手法は去年DJ Emmaさんの『Acid City 2』っていうコンピレーションシリーズのラストトラック(“Ratchet Acd”)で多用し始めたかな。
―― サンプリングに近い手法ですよね。
Gonno:そうですね。その音の質感が欲しくて、ノーマルポジションのテープで録って、それを更に回転数を落として取り込んでっていう。そうすると高音のツヤツヤした嫌な感じが消えて。ソフトウェアでもStuderやAmpexのテープシミュレータとかあってそれも使いますが、Studerのシミュレートだとどうしても高級感が出ちゃうし、ソフトウェアは個体差も無いので、使う人がみんな同じ音になっちゃうんですよ。
―― 最近はソフトウェアでも十分に作って完結することはできますし、そういう方々も実際にいますけど、Gonnoさんはハードウェアを徐々に増やしていったのは何でなんですか?
Gonno:試してみようって感じで買ってるだけなんですよね。実際言うと。例えばSo Inagawaくんと話したら、彼はもうソフトウェアだけで充分っていう話をしてたんだけど、彼の音楽はフロアでとてもよく鳴るじゃないですか。多分彼は良い音というのを知ってるからそう言えるんだと思っていて、ハードウェアって1回その音を知っちゃえば、調整に時間を掛ければソフトウェアだけでも良い音は出せると思うんですよね。ハードウェアを経由してソフトウェアを使うと、音のミックスの仕方も変わっていくんですよ。だから僕はあんまりハードウェアだから音が良いとか、そういった事は思わないです。それぞれに使い道があって、例えばMoogもSub PhattyとLittle Phattyでは全然音が違って、Sub Phattyの方が廉価なんですけど、低音の抜けがLittle Phattyより凄く良くて。だから機材によって特性があるので、一概に「このヴィンテージシンセを使ったから音が良い」とか「このモジュラーシンセを使って、このオシレーターを使って、このフィルターを使って、このアンプだから」って良い音になるとは限らないと思うんですよ。適材適所なんですよね。
―― いまのGonnoさんのセットアップは、10年選手のKorgもいて、新入りもいて、っていう、凄い10年の蓄積感がある布陣なんですね。
Gonno:10年、そうですね。恥ずかしい話なんですけど、しかも実は使ってるエレキギターは所謂借りパクしてるものなんです(笑)。アコギも中学生の時に友達とガットギターと貸しっこしたものを返してないままで(笑)。この誌面で謝りたいです。
―― それがアルバムの一音になるっていうのも、また思い出として良いですね。ギター以外の楽器は弾かれたんですか? 今作はシンセ以外に、ピアノの音を結構使っているように聴こえたんですが。
Gonno:そうですね。ピアノはソフトウェアで、Native InstrumentのものかEastwestのものです。Kuniyukiさんのようにバシバシ弾けるわけではないんですが、コードやフレーズを多少弾いたりはしました。
―― ちなみにアルバムのマスタリングはKuniyukiさんがされてるんですよね。
Gonno:はい。アルバムの音が良いと思われたら、それはKuniyukiさんのおかげです。前に〈mule musiq〉のコンピレーションに参加した時に初めてマスタリングして頂いたんですけど、僕のミックスの出来上がりがあまり良くなかったので、これでマスタリングしていただくのは大丈夫かなとか思ってたんですけど、一発でとても良い音になったんですよね。
―― Kuniyukiさんとは普段からメールのやり取りをしたり、親交はあるんですか?
Gonno:仕事以外でメールをやり取りすることはほとんど無いんですが、色んなところでばったりお会いしますよ。お知り合いになれたのが3~4年前ぐらいですかね。野外イベントで一緒になって。その時のKuniyukiさんのライブは凄かったですよ。Kuniyukiさんの出番が朝だったんですけど、Kuniyukiさんの登場と共に朝靄がブワーッと出てきて。僕は寝起きだったんでお酒は入ってなかったんですけど、Kuniyukiさんのプレイ聴きながら、ブースを見てたら、だんだんKuniyukiさんが木に見えてきて。
―― 木、ですか……。
Gonno:「これは樹木が音出してるな」みたいな感じ。忘我というか、全然エゴの無い音世界みたいなのが広がってて。とにかく凄かったですね。
―― それ凄そうですね……。木に関連してなんですけど、今作のアートワークはキノコのイラストですよね?
Gonno:Stefan Marxのイラストですね。〈Endless Flight〉のジャケットをもうずっとやってるんですよね。
―― 〈mule musiq〉関連の作品ではお馴染みのイラストレーターですね。
Gonno:彼はスケートカルチャーの人なんですよね。実は他の方から言われるまで全然知らなかったけど。〈Endless Flight〉と〈Smallville〉のジャケットの人だっていう認識でした。
―― 前にStefanのInstagramにカラフルなイラストが描かれたボードの写真がアップされてましたね。どうしてキノコのイラストにされたんですか?
Gonno:アートワークを「この中から選んでもらえますか?」と何枚か見せていただいて、これが1番アルバムにフィットしてるかなと思ってこれにしました。なのでこういう絵を描いてくださいって頼んだわけではないです。選んだのも感覚的にですね。キノコが良かったというよりかは、Stefanのイラストの中でもより可愛らしくドリーミーで、かつトリッピーなものが良いなと思ってこれにしたんです。
―― ここ最近のEPやシングルから受ける印象がフロア向けのイメージだったからかもしれませんけど、今作はいま仰られてたようなトリッピーな面もありますし、クラブのアフターアワーの少しクールダウンしていくというか、クラブから外に出てチルアウトをするような雰囲気もかなり含んでいると思うんです。で、GonnoさんはDJをされているから、DJをしてフロアを熱狂させた後の時間帯が関係しているのではないかなと思ったんですが。
Gonno:いや、そういう部分よりも、確かに僕はDJだから、クラブに行ったことがない人からすると「テクノとかハウスのDJの人が作ったアルバムだから、ドンツクドンツクいってるんでしょ」ってイメージするだろうと思ったんですよ。だからそれに対して「DJはそういう要素だけじゃないんだぞ」って部分を聴かせたかったんだと思います。そもそもDJって踊らせるだけじゃなくて、基本的には色んな音楽の含蓄や造詣があって、色んなものが好きなんだけど、それを引っくるめてみんなを踊らせたくて、みんなに聴かせたくて、それでそれをミックスしたりノンストップにしてDJをやってるんだと思うんです。そういう側面を自分の作品でアウトプットしたかったんですよね。
―― 普段GonnoさんがDJをして組み立てている時に用いてる要素たちを、今度はアルバムという形に組み立てて表現しているっていうところなんですね。
Gonno:そうですね。そういう意味で言うと、正直最近ダンスミュージックに閉塞感を感じてて、テクノやハウスのパーティーならダンスフロアでかかっているものはBPM120~130で鳴ってなければいけないみたいな、そういう予定調和がちょっとつまらなくて。昔から嫌いなんですよ、そういった予定調和というか、様式美が。「なんでVan Halenの速弾きができないの?」、「イングウェイの早弾き凄くない?」とか、もとから本当に興味なくて。別に弾けなくても良いじゃんって思ってた。僕はいつになってもそういった様式美から逃げてきた人で、そういう性格から、今作も「DJやクラブミュージックはそれだけじゃないんだよ」っていう表現をしたかったんですよね。踊らせるだけじゃなく、音楽を好きになってもらうことができるのもDJの役目なんじゃないかなと思いますからね。
―― DJをする時にトラックを構成していくのとは打って変わって、アルバムとして構成した時に意識したこととか、今作の構成に関して自信を持ってらっしゃる部分はありますか?
Gonno:さっきも言ったんですけど、ダンスミュージックというだけじゃなくて、クラブツールとしてのみ存在するのではなく、例えば車の中でも良いし、電車の中でiPhoneで聴くのでも良いし、そういうシチュエーションを問わないっていう部分はやっぱり意識しましたね。そこは胸を張って良いかなと思います。
―― 確かに、僕や色々な人にとっての「1日=24時間」に置き換えて聴くこともできますし、Gonnoさんというアーティストを通してアルバムを聴くと「10年間」とも捉えることができる時間的な流れのある作品ですね。
Gonno:それってパーティーでも言えることですよね。インタヴューでしか見たことがないですけど、「The Loft」のDavid Mancusoとかも一晩の理想的な選曲は、太陽が沈んで、また太陽が上がるような選曲をするっていう話をしてて、僕もそれが1番だなとずっと思っていて。僕は曲と曲をミックスするので厳密なプレイスタイルは違いますが、一晩でストーリー性がある、2時間や3時間でもストーリー性があるっていうのが好きなので、アルバムも同じようにストーリー性が反映されてるんだと思います。
―― DJをする時は、セットリストをある程度決められてるんですか?
Gonno:いや、全く決めないです。決めた方が良いんじゃないかって思う時もあるんですけど、例えば40分の時とか。そもそもDJが40分で何を表現できるんだろうって思うんですよ。でも決めないですね。やっぱり予めストーリーを決めても、当日になって、その場にいるお客さんが求めている日の入りじゃないかもしれない、求めていない日の出になってしまうかもしれないっていう想定をしてるんですね。例えば今日は雨が降ってますけど、室内でも、雨の日のクラブパーティーと晴れのクラブパーティーとか、いまの時期のクラブと冬のクラブは違うじゃないですか。で、フロアの雰囲気っていうのは、お客さんの数によっても違いますし、クラブ単体でも違いますし、パーティーによっても違いますし。
―― 出番前のDJがどんなプレイをしたかにもよりますしね。
Gonno:そう。だから全然決めないですね。その場で成立するストーリー性みたいなものを考えてますね。
―― 10年の間にDJとして日本全国、ヨーロッパを巡ってプレイしてきた経験が技術的に活かされている部分は、今作の中にはあると思いますか?
Gonno:あまり考えたことなかったけど、たぶんリズム感覚は鍛えられたんじゃないでしょうか。BPMが遅い曲でもグルーヴがある、トランス感がある、みたいなダンスフロア特有のものは今作にも出ているかもしれません。こんなこと言うとインタヴューの身も蓋もないけど……自分の音楽って他の人のものと比較するのはなかなか難しいんですよ、バイアスがかかっちゃうんで。それでも例えば、あるエレクトロニカのアーティストがフロアライクな曲を作りましたって聴いてみたら、客観的に「これは良くないな」って思ったりする時は多々あって。尊大ですが、そう思うときは、自分の方がダンスフロアのことをよくわかってるからだろうなっていうのはありますね。
―― 先ほど、例えでFour TetやBibioっていう名前を挙げましたけど、彼らの音楽はお好きですか?
Gonno:Four Tetは大好きですよ。Bibioも最近は追えてないけど以前よく聴いてました。Bibioって、僕が10代の時に聴いてたロックの系譜の延長線上なんですよね。だから違和感無く、すんなり入ってくる。Four Tetはいまでも曲の作りとか、聴いててハッさせられますね。よく聴くとリズムがもの凄くポリリズミックになっていたりとかね。とっても影響されています。
―― Four Tetはサンプリングとかリワークとか、全てにおいて引き出しが多いですよね。
Gonno:そうですよね。前に何かのインタヴューで読んだんですけど、彼が多作な理由は、移動中に飛行機の中でラップトップを使ってどんどん作っちゃうらしいですよ。
―― 以前、Nathan Fakeについてもツイートされてましたよね。彼の音楽も、今作含め、最近のGonnoさんの作品と通じるところがあると思うのですが。
Gonno:Nathan Fakeも大好きですよ。Four TetやBibioもそうだけど、全員イギリス人だし、もしかしたらイギリスの感じがもとから好きなのかもしれないですね。イギリスってダンスミュージックでも、ドイツの機能美を追求する感じより、どこかパーソナルな部分というか、叙情性が出て来ちゃうところってありますよね。そういうアーティストが多い気がして、そこが好きなのかな。コアなダンスミュージックリスナーは逆に「そんなの乗せないでいいからもっと身体に機能してくれよ」って感じの人もいると思うけど。もともとUKロックとかが好きだったんで、たぶんそういったものが性に合うのかもしれないですね。
―― 音楽の好みとか、音楽的なリファレンスは10年間で変わりましたか?
Gonno:昔は具体的にこういうサウンドにしたいなっていうのがあって、リファレンスになるべく近づけて近づけて、サウンドエンジニアリングもなるべく近づけてっていうのがあったんですけど、最近はそういうのが無くなっちゃいました。逆に、いままで近づけようと思っていたものともっと違うものを、ってなった。例えば、Nathan FakeやFour Tetは大好きですけど、他にも大好きなアーティストは沢山いるし、またそれと同じようなものを作っても彼らに失礼だなって思いますし。好きだから故にそれを尊敬をもって踏襲して、かつ自分らしいものをなるべく作ろうとしてます。
―― でも、無くなったっていうことは、Gonnoさんの中でご自身のスタイルが出来上がった、ということなんじゃないですか?
Gonno:そうなんですかね……だと良いんですけどね。でも自分のペースができてきたっていうのは少し実感がありますね。亡くなってしまった〈W.C. Recordings〉のSalmonくんが生前ずっと言われてたことなんですけど、まず「音楽やるなら誰もやってないことをやるべきだ」って言っていて、あと、「ゴンちゃんはしれっと出てくるポップさが良いよね。それは大事にした方が良いよ」って昔に言われたんですよ。ポップさって物凄く奥深いものなんだけど、その2つはいまでも自分の中で意識していることで、この2つを守ってきて、いまの自分の音楽が形成されてるのかもしれませんね。
End of interview
リリース情報

Gonno『REMEMBER THE LIFE IS BEAUTIFUL』
Release Date : 2015.07.29
Label / Cat No. : ENDLESS FLIGHT / CD15
Price : ¥2,100 + 税
<Tracklist>
01. Hippies
02. The Worst Day Ever
03. Stop [Album Version]
04. Confusion
05. Beasts In Your Mind
06. Across The Sadness [Album Version]
07. Already Almost
08. Revoked
09. The Island I’ve Never Been
10. Green Days [Album Version]