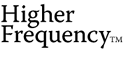Highlight
Pioneer DJM Engineer Interview
Text & Interview : Yoshiharu Kobayashi
2013.5.8
CD/マルチ・プレイヤーのCDJシリーズと並び、プロ・アマ問わず世界中のDJから厚い信頼を寄せられているパイオニアのDJミキサーシリーズ、DJM。その最新モデルであるDJM-750が6月に発売されることで、パイオニアが誇る4chミキサーシリーズの新たなラインナップが完成する。これを機に、パイオニアの開発担当者の皆さんから、その開発秘話や設計思想などについて、たっぷりとお話を窺った。この対話を読んでもらうことで、常に現場の声を大切にしながらも、新しい挑戦を続けているからこそ、パイオニアのDJMシリーズがDJミキサーのトップ・ランナーであり続けているということが分かるはずだ。
※ 2019/7/1 追記
2013年の取材当時は、Pioneer株式会社のDJ事業部であり、2014年8月よりPioneer DJ株式会社として独立しています。取材に応えていただきました開発担当者の皆さまの在籍部署は取材当時の情報になります。また、DJM-750は現在、生産終了となっているモデルです。

DJ機器、技術部門の統括部長。DJMシリーズ の初代機である DJM-500 を作る前から、20数年の間、パイオニアの中で DJ 機器を作り続けているエンジニア。

設計部所属。ハードウェアの製品設計をしており、主に DJ ミキサーやエフェクターに携わっている。

ミキサー、エフェクターのソフトウェア開発に携わっているエンジニア。今回取材に応じてくれた3人の中で最も若手。自身もDJとして活躍中。

――では、早速お話を訊かせてください。御社が初めて発売した DJ ミキサーは DJM-500 ですが、これを作ったきっかけは?
山田 : このミキサーを出す1、2年ほど前に、日本の型番では CDJ-50、世界の型番では CDJ-500 というプレイヤーを作ったのですが、プレイヤーを作ったからにはミキサーにもチャレンジしたいということで作り始めました。実はその当時、DJ 専用のミキサーは非常に少なかったんです。バトル用の 2ch ミキサーはたくさんあったのですが、多チャンネルでハウスなどをかける DJ 用のミキサーがなかったので、作ってみようとなりました。一番のポイントは、この縦長のデザインです。
――当時のミキサーは、横長というか、いわゆるラックマウント式が主流だったのですか?
山田 : そうですね。ラックイヤーの付いた 4ch が主流でした。なので、縦長にする、それからプレイヤー同士を近づけた形で 4ch を実現するというのが非常に大きなコンセプトでした。また、DJ のためのエフェクターを搭載させたいというのも最初からありましたね。例えばギターの世界だと、エフェクターを使うことはタブーではなく、むしろそれを使うことで音楽もパフォーマンスも進化しています。なので、ライヴ・パフォーマンスをする DJ にとって、ギターの世界と同じくらいに、エフェクターは大切になっていくだろうという勝手な思いが当初からあったんです。

――DJ は単なる選曲家ではなく、曲の演奏者なんだというイメージで最初からやってこられたというわけですね。
山田 : そうです。DJM の製作初期の段階からアドバイスをいただいていたヒップホップの方にプレイを見せていただいたんですが、それで 「DJ は単に曲をかけているのではなく、演奏しているんだ」 とわかったんです。そういう意味ではロックのアーティストとも同じですし、オーケストラの指揮者と同じくらいに大切な存在だとも言えると思います。その方がプレイすることで、同じ曲も違って聴こえてくるわけですから。
――実際、最初はどういった DJ からアドバイスをもらっていたのですか?
山田 : 最初は日本のヒップホップの皆さんから色々と教えていただきました。例えば、DJ YUTAKA さんとか、当時 YUTAKA さんと一緒に活動していらっしゃった DJ HONDA さんですね。そういった皆さんから知っている方を紹介していただいて、その後に4つ打ちの方たちにもたくさんのアドバイスをいただいています。
――実際に完成した DJM-500 を見てもらった時は、DJ からの反響はいかがでしたか?
山田 : 実は、まず手作りのコンセプト・モデルを作ったのですが、その時はエフェクト部分を(完成品のように縦ではなく)真横に入れてしまったんですよ。ラックマウント・エフェクトというものがありましたから、最初はそのイメージで真横に入れてしまいまして。でも、それを世界中に持って歩いたら、「縦のラインが訳わからなくなるようなものを入れるな」と皆さんにお叱りを受け、出張から戻ってきてすぐ縦に直しましたね(笑)。そんなレベルで、本当にノウハウのない状態から作り始めたんです。しかし、試行錯誤を経て、でき上がったものを持っていき、CDJ と一緒に使っていただくと、「よくやった!」 とすごく褒めていただきました。実際、「いやいや、そんなに褒められていいのかな?」と思ってしまうくらいで。でも、そうやって褒めていただいたことが嬉しくて、その後20年間も続けていくことができているんだと思いますね。


――DJM-500 に続いて発表されたのが、DJM-600 ですよね。これでパイオニアの DJ ミキサーは世間に広く普及し、スタンダード機になった印象があります。これはどういったところをポイントに作られたのですか?
山田 : DJM-500 でご意見いただいた点はとことん直そう、というのがまずはありました。大音量のクラブで使う際のノイズ対策ですとか、そういった基本的な部分をしっかりと改善しようと考えましたね。でも実は、DJM-600 を作る時に、もう私達はデジタル・ミキサーでまだ見ぬ世界を提案したかったんです。しかし、当時の部品を集めて何度試算をしてみても、納得の行く値段と性能にはできませんでした。そこで、アナログという形でできる限りのことはチャレンジしようということになったんです。そういった意味では、わりと真面目に(笑)、地味な改善を色々としたという位置づけではあります。
――しかし、次の DJM-1000 では、念願だったフル・デジタルを実現したわけですね。
山田 : はい。それまでは DJ の方の視点で使いやすいものということで、DJM-500、DJM-600 と作ってきたわけですが、DJM-1000 はそれとはまた別に、クラブのエンジニアの視点で見てもパーフェクトなものを作りたいということで出来上がったものです。その中のひとつの要素として、音質をトップ・エンドまで持っていくというのが一番のコンセプトでした。音質を考えると、アナログで行くか、デジタルで行くかという二つの選択肢があったのですが、当初は両方とも試作をしたんです。そして、どちらの方が DJ ミキサーとしての最高の音が出るかと試した結果、ここは一気にデジタル化しようということになりました。飽くまで音のためのフル・デジタル化です。本当に音にこだわったモデルですね。
――当時、世間的にデジタル・ミキサーはどの程度普及していたのですか?

山田 : 制作の世界ではデジタルの波がドッと来ていたのですが、クラブのミキサーの世界では、デジタルというだけで音を聴く前にネガティヴな反応をいただくこともありました。もちろん、音に関しては、色々なエンジニアの方に聴いていただき、アナログに遜色ないどころか、アナログにはできない領域までできるように試作を繰り返しました。ただ当時は、アナログの方がいい音というイメージが、まだ半分くらい残っている時代だったんです。そういった意味では、チャレンジでしたね。



――それからも、後継機のDJM-700、DJM-800 などが発表されていくわけですが、この時こだわった進化のポイントは何だったのでしょうか?
山田 : DJM-800 でやろうとしたのは、DJM-1000 で初めて取り組んだ24bit/96kHzのフル・デジタルを、我々の本流であるこちらの形でも進化させることでした。また、ひとつ大きかったのは、SOUND COLOR FX を各チャンネルの EQ と CUE ボタンの間に入れることでしたね。初代ではそこにエフェクターを付けようとして皆さんに怒られましたので(笑)。
小泉 : DJM-500 でエフェクトを真横に入れて DJ から怒られたという話は、実は僕も今日、初めて聞いたんですよ(笑)。でも、逆に DJM-800 の方は色々な形があった中で、SOUND COLOR FX を横に入れるという形でバンッと行けたんですよね。DJM-800 では、SOUND COLOR FX はもちろん、その横の BEAT EFFECTS も新しい音を作ろうと設計したのですが、デジタルでエフェクトを作るのは初めてでしたから、その点はすごく苦労しました。搭載されているチップが DJM-800 から新しくなったこともあり、一から作り直しましたので、作るのに1年以上かけたんです。ただ、作り直すにも、DJM-600 までのエフェクトの音質や使い勝手を崩さないようにしつつ、使いづらいところは直さなくてはならないので、そこも本当に大変で。また、これは山田からも当時言われたのですが、意識したのは5年後でも通用する、5年後にはスタンダードになっているエフェクトを搭載するということでしたね。それは音の種類もそうですし、使い勝手という点でもそうです。
――なるほど。一方の DJM-700 は、どういったイメージで作られたのですか?
奈良野 : DJM-700 は私がまさに担当していたんですが、これは DJM-600 の後継機という位置づけです。そのため、フル・デジタルの部品を搭載しながら、DJM-600 と同じコストまで下げたいというのが一番の狙いでした。かなり取捨選択はしつつ、しっかりと大事なところは残すということで苦労したのを覚えています。あとは、DJM-600 であったクラブでのノイズ系の問題を、しっかりとフィードバックして修正していったというところでしょうか。
――エフェクトや音質面以外にも、DJM-800 や DJM-700 に込めたこだわりはありますか?
小泉 : DJM-600 は MASTER のレベルがフェーダーなので操作しづらいと結構言われたため、DJM-800 ではツマミにしました。でも、この間、昔の図面を見直したら、MASTER のツマミも今の右上ではなく、最初は DJM-600 で MASTER のフェーダーがあったのと同じ部分にただツマミを置いただけだったんです。今振り返ると、すごく試行錯誤の跡が窺えるなと思いましたね。
――作っていく段階で、ボタンなどの位置関係も含めて、結構変わっていくものなんですね。
山田 : はい。細かい変更点としては、例えば、DJM-800 は MASTER 部分の幅が DJM-600 より細くなっていますし、EQ 同士のツマミの距離は DJM-600 よりちょっと長くなっているんですよ。当時は埋め込みでミキサーを使うお客様が多かったので、全体のサイズが変わると怒られてしまうという状況があったんです。なので、どうにかこのサイズの中で細かく色々と調整しているんですよ。僕らとしては、ギリギリのところをキープしつつ、その中に操作性を詰め込んでいるので、もうこれ以上の「福笑い」は無理だなというくらいです(笑)。

――ただ、次の DJM-2000 になると、かなり見た目も変わりますよね。中央に大きなディスプレイがありますし、サイズも大きくなりました。
山田 : そうですね。このへんでサイズの縛りから勝手に解放されてみました(笑)。今までお話をさせていただいたミキサーは、アナログから始まって、その後は内部がデジタルになっていきましたが、ユーザー・インターフェースはアナログの時代と変わらないものをキープするというコンセプトだったんです。その点は少し古風なところがございまして。しかし、DJM-2000 ではそこから一歩踏み出し、ディスプレイのエリアとその上の部分はフル・デジタルにしかできないものにチャレンジしようと考えました。上の部分は、弊社の EFX でやっていた、ダイレクトにエフェクトや拍を選ぶというシステムを採用しています。ディスプレイ部分に関しては、マルチタッチでエフェクトをコントロールしてみようとした結果です。今となっては iPad などでこの世界観も広く普及しましたが。


小泉 : エフェクトに関しては、DJM-2000 だとビートを飛ばしたりできるので、よりパフォーマンス寄りにもなっていますね。チャンネル選びも、ダイレクトでわかりやすくなりました。
山田 : それまでの DJM では、エフェクトは右寄りで縦一列に入っているんですけど、今度はもっとユーザー・インターフェースを開放して、「真ん中でどうだ!」 っていう(笑)。最初は真横に置いて怒られて、そっと端に置いておくことにしたんですけど、遂に大きくして真ん中に置いてしまったというのが本音だったりするんですよ(笑)。
――続いては DJM-900 nexus ですが、やはり気になるのは、手前のところに従来のミキサーにはない、でっぱりがあることですね。
山田 : これを最初に採用したのは、SVM という映像用のミキサーでした。レコーディングや PA の卓ですと、軽く手を置く部分があって、ゆったりとプレイできるので、そのイメージです。実は、私が20年前、一番最初に一体型のプロト・タイプを作った時は、他のミキサーから 「あご」 の部分を外して持ってきて、自分で削ってフロントにつけたんです(笑)。それで、「こんなふうに手が乗せられるものにしたいな」 と言っていたんですよね。
――最初に考えていたものが、ここで遂に復活しているんですね。他に、DJM-900 nexus で特徴として挙げられる部分は何でしょうか?
奈良野 : DJM-900 nexus は DJM-800 の後継という位置づけなので、4ch のスタンダード・ミキサーの一番上ということになります。やはりパフォーマンス寄りの DJM-2000 とは違うのですが、その後に出ているということもあり、高音質の回路など音質面は継承されています。そこがハード的には一番大きいところですね。

山田 : ここでひとつチャレンジをしたのは、USB と LAN を装備したことです。PC に保存した音源をプレイされる方が増えていますので、その方たちにとっても快適に使えるように、天面に USB の差し口を持ってきました。後は、CDJ-2000 を使うと、LAN 端子で機材同士を全てリンクできるようになっています。その仕組みを、nexus (繋がり、結びつき)と名前をつけてみたんです。
奈良野 : テンポの同期情報を始め、いろんな情報を LAN を通して共有できるので、エフェクトもビート単位できっちりかけられるようになっています。
山田 : コンピューターの中では全部が同期していて当然ですが、自分たちで好きな機材を好きなように用意して、それが全部リンクして同じように動いてくれたら快適だろうなという発想ですね。
――X-PAD も DJM-900 nexus の大きな特徴のひとつですよね。
小泉 : DJM-800 は世界中で使っていただけたこともあって、そこから形を崩しづらい。ただ、その一方で、DJM-2000 はパフォーマンスがしやすくて受けたところもありましたので、DJM-900 nexus では X-PAD という操作的にも新しいものを取り入れ、そこでパフォーマンス寄りのエフェクトをかけられるようにしました。従来のエフェクト操作だと、ツマミを回して、選んで、エフェクトをオン、っていう3つのアクションが必要だったのに対し、ここではビートを合わせると同時にオンに出来るという手軽さが特徴ですね。
山田 : 実は、これもギターのエフェクターから来ているんですよ。あれもポンッと踏むことで、エフェクトのオン、オフを操作しますから。また、段々と世間的にもタッチパネルが普及し、他社でもタッチパネルを使った新しいアプローチが出てきた中、うちもこの小さなスペースを使って楽しくエフェクトをかけることができないだろうか、という発想もありました。つまり、ここには DJM-2000 の世界観の一番エッセンスの部分だけを入れてみたんですよ。


――続いて発表された DJM-850、DJM-750 にも個性的なエフェクト機能が搭載されていますよね。
山田 : DJM-850 と DJM-750 は、それぞれ違う設計チームがやっているのですが、ワン・ポイントは競争して個性を出していい、ということにしました。それが DJM-850 だと、各チャンネルに配置された SOUND COLOR FX のツマミと、その左上にある BEAT ボタンですね。SOUND COLOR FX でできることが、DJM-900 nexus よりもひとつ大きく増えています。一方の DJM-750 は、SOUND COLOR FX のツマミはひとつですが、BOOST というボタンで今までにはなかったオリジナルな演奏ができるようになっています。このへんは DJ の方からいただいた意見を反映させたというよりは、エンジニア・チームの中で工夫した結果生まれたものです。
小泉 : DJM-750 は、SOUND COLOR FX のノブが一個しかないから面白くないのではなくて、一個しかないけれども色々な音が出るようにしたり、ノブ自体を大きめにすることで回しやすくしたりとか、そういうところを意識しました。ノブを回すスピードが速いか遅いか、BOOST のオン、オフでも効果が変わってきますし、また BOOST を押したということに対する音でのアクションも加えています。
山田 : ノブはひとつしかないですが、結構音のバリエーションが出る仕組みなので、練習していろんな音を出してもらえたら嬉しいですね。
――楽しみですね。DJM-850 のエフェクトに関してもご説明お願いできますか?
山田 : SOUND COLOR FX は、回していないと効果がステイします。それは、ある部分ではコントロールしやすいんですが、ある部分では物足りなくなる人もいたのは確かです。それで DJM-850 では、BEAT ボタンを押しておくと、音楽の強弱に応じて SOUND COLOR FX のツマミが回ってくれるようにしたんですね。その結果、ひとつの同じエフェクターとは思えないくらいに多彩な音が出るようになりました。例えば、マルチ・トラックの音源を BEAT SYNC した状態で、BEAT ボタンをオンにしっ放しにしておくと、思わぬフレーズがボンボン飛び出してきます。たまに SOUND COLOR FX のツマミを回してみるだけで、不思議なブレンドが生まれるんですよ。これはぜひ試していただきたいところです。


――DJM シリーズではノブやフェーダーも進化を続けていますよね。その開発エピソードも教えて下さい。
山田 : ノブは開発当初から非常にこだわっていました。例えばノブの太さは、海外の大柄な DJ の親指の太さとかも考慮しないといけないわけです。つまり、操作感に関しては、自分が触って回しやすいだけではダメなんですよね。DJM-500 で出来なかったことには、DJM-600 で改善し、DJM-800 で改善し、とやってきたわけですが、特に DJM-800 の時にツマミはスタンダードなものができないだろうか、と思いながら作っていました。
小泉 : EQ のツマミは DJM-600 ではプラスチックだったのですが、ずっと触っていると痛いということで、DJM-800 では素材を変えているんです。触り心地がだいぶ違うと思います。
山田 : そして 現行のDJM で使われているものは、DJM-800 で作ったツマミが原型なのですけれども、これに至るまで、ものすごくたくさん作ったんです。長さ、太さ、へこみの形状の違い、それにゴムのかけ方ですとか、「いつまでこんなの作るんだ?」 というくらいに何個も作りましたね(笑)。ほかにも、DJM-900nexus では MASTER のツマミが他よりも少しだけ低いとか、BALANCE のツマミは更に低いとか、そういうところにもこだわり抜いています。プレイ中に音のバランスが変わってはいけませんから、このように高さを変えておけば、触った瞬間に 「あ、違うものを持ってしまったな」 とわかるんですよね。こういったこだわりがどれだけお客様に伝わっているかは自信がありませんが、むしろ気付かないくらいに自然なものとして気持ちよく使っていただけているとしたら、それが一番いい状態なのかなと思っています。
――全般的に、音質面はどのような設計思想なのかも教えてもらえますか?
奈良野 : 原音に忠実というのを大前提とし、バランスが取れているようにしています。クラブにある PA 機材に変な影響を与えないように、ということですね。
山田 : 実は民生の商品は、DJ 機器で出せるほどの大音量と低音は求められていないんです。結局、(環境的に)出すことができないので。実際にクラブに持ち込でわかったのですが、今のクラブのトラックは本当に低音の方までしっかりと音を作っていますし、いいクラブの音はロウ・エンドの伸びが本当にすごい。なので、こういったミキサーは民生のものよりもワイド・レンジで作っています。特に低音に関しては、一般のステレオでは気にならない鳴り方とかスピードにも気を使っていますね。ただし、普通のオーディオ機器のようにマニアックなサウンドがするとか、ロックに最適だとかジャズに最適だとか、そういうチューニングではありません。先ほど奈良野が言っていたように、至ってフラットに作るというのが、ひとつのコンセプトです。エンジニアさんの視点に立っても、クラブのハコの鳴り方を上手くコントロールしようとするなら、一番素直に対応が効く癖のなさがいいであろうという結論です。
――それにしても、DJMシリーズに限らず、パイオニアのDJ機器には次々と新しい機能が搭載されていき、いつも驚かされてばかりですが、その発想のヒントはどこにあるのでしょうか?
山田 : トップ・プロの方からアマチュアの方、そして初心者の方まで、DJ の皆さんからのフィードバックが一番の原動力であることは間違いないです。それと同時に、音楽そのものも時代と共に変わってきているので、我々としてはそこもポイントになっています。
――音楽は時代と共に変わるとのことですが、今後 DJ プレイはどのように変わっていくと思われますか。また、それに合わせて DJM はどのような進化を遂げることになりそうでしょうか?
山田 : DJ ミキサーが DJ にとってどういう存在かというのは、この20年、30年で同じ部分もありますし、変わってきている部分もあります。それは DJ の方たちにとって、DJ プレイが昔のいわゆる 「クラブ DJ」 という世界観だけだったところから変わってきているからだと思うんです。今や SYNC を使って楽曲を合わせる機能は普通に使われていますが、ちょっと前まではピッチ・ベンドをしてピッチを合わせるというのは、基本的なスキルとして非常に重要でした。もちろん、今でもその世界はありますが、もっとたくさんのトラックを使ったり、生で演奏する人と一緒にやったりなど、どんどん幅が広がっています。おそらく、ミキサーの果たす役割は、演奏面でもっと重要になっていくのではないでしょうか。その点では、僕らも機材を通してもっと違うアプローチをできないかと考えています。EDM の躍進とか、ヒップホップがワールドワイドな音楽になったことに我々もワクワクしているのですが、そのように多様性が増している中で、もっと変わっていくことが求められるのではないかなと思いますね。
それから、僕が DJ の方を見ていて、いつも感心させられてしまうのは、テクノロジーの進化を拒まないというのが基本にあることです。例えば石野卓球さんは、ドイツでプレイされる時にアナログでやっていらっしゃったんですね。なので、僕も朴訥に、「卓球さん、うちの製品を褒めてくださっていますが、やっぱり使いづらいですか?」 と訊いたんです(笑)。そしたら、「いや、僕がドイツではアナログで回すのは、お客さんが求めているからですよ」 という答えだったんです。それを聞いて、これはすごいなと。DJ の方はテクノロジーをどんどん取り入れるのですが、お客さんのために必要なスタイルもしっかりと見せている。ターンテーブルも CDJ も PC アプリケーションも必要だということを拒まずに、積極的に取り入れているわけです。そのおかげで、我々もずっと変わらない同じ楽器を作り続けるのとはまた違う仕事をさせていただいているので、非常に楽しいですね。

――最後に、特集をご覧の皆様に、メッセージをお願いします。
小泉 : これからも、新しいだけではなくて面白い音を作っていきたいと思っています。かつ、わかりやすく使いやすいものですね。
奈良野 : 私はハード設計なので、使いやすさや信頼性、あるいは高音質ですとか、そういうところは突き詰めていきたいので、楽しみにしていただきたいです。
山田 : 僕はこういった仕事を DJ の方たちとできるのが本当に楽しくて仕方ないんです。今後もダンス・ミュージックやそれを支える DJ の方、そしてそれを更に下で支える(笑)パイオニアというメーカーとして、もっと面白くなる音楽シーンに少しでも参加して力になれたらいいかなと思っています。ぜひ今後ともよろしくお願いします。