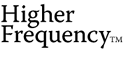Highlight
HISTORY of UK MUSIC 1970-2016
Text : Hiromi Matsubara
2016.3.25
ロック、パンク、エレクトロ、レイヴ、グライム……ムーヴメントを起こし、特別な存在感を世界に示し続けてきたUKの音楽。数十年前の曲も今に至るまで長い間語り継がれ、最新系/流行の音楽には真っ先に多くの注目が寄せられています。ガレージから、ベッドルームから、そしてストリートから発せられた、社会に対する感情を根元的なエネルギーとするいくつものメッセージとサウンドは、アーティストだけでなく市民をも結ぶ証となり、世界的なヒット曲へと変貌を遂げてきました。本企画では、1970年〜2016年の約40年にわたって生まれてきた、そんな「これぞUKの音楽!」と呼べる特別な楽曲を50曲紹介していきます。お届けするのは、1914年にイギリスで誕生して以来、長年にわたってサッカーやラグビー、テニスなど英国のスポーツに多大な貢献をし、昨今はロンドンの都会的なイメージと「音楽、UK、ファッション」に裏付けられた素材/色/デザインを表現に落とし込んだフットウェアを展開するブランド〈Admiral Footwear〉。毎週更新予定なので、本ページと、〈Admiral Footwear〉とHigherFrequencyのSNSを随時御覧ください。それではUKの音楽を振り返る旅、スタートです!
1970
The Beatles “Across the Universe”
今回の企画の始点である1970年は、The Beatlesが最後のアルバム『Let It Be』をリリースした年です。この“Across the Universe”は、かの有名な「Get Back Session(原点に立ち返るセッション)」から生まれた曲でもなく、アルバムのために作られた楽曲でもなく、いくつかヴァージョンがある曲ですが、作詞者のジョン・レノンはフィル・スペクターがアレンジを手がけた『Let It Be』収録ヴァージョンを賞賛していたそうです。またジョンは、「本当に良い歌は、メロディーがなくても歌詞だけでその価値を見出せる歌であり、それに該当する曲こそが“Across the Universe”だ」とも述べています。
1971
The Who “Baba O'Riley”
UKには、時代と共に新しいものを取り入れて変化をしながらいくつもの名作を残してきたバンドが山ほどいますが、その中でも特に後世に多くの参考点を残したバンドといえばThe Who。「四重人格」という邦題をよく目にする『Quadrophenia』も言わずと知れた傑作ですが、彼らが初めてシンセサイザーを作曲に取り入れながらも、あくまでロックスタイルを貫こうとしている『Who's Next』もかなりアヴァンギャルドで刺激的。オープニング“Baba O'Riley”冒頭のシンセリフは今もたまにハウス・トラックで耳にするような気がします。
Led Zeppelin“Stairway to Heaven”
今もギターを弾き始めには“Stairway to Heaven”のイントロのアルペジオを練習するのが定番なんでしょうか。あまりにも多くの人がギターの試し弾きでこの定番アルペジオを弾いていたため、一部の楽器屋では禁止されているというエピソードもあります。そこまで定番として浸透しきった2016年になって、まさかこのアルペジオの盗作を巡る訴訟が起きるとは思いませんでした。でも、当然、アルペジオがこの楽曲の醍醐味なわけではなく、8分間にわたる楽曲の構成と、身体に何かが宿って昇天しそうなクライマックスが最高なのです。
T. Rex “Get It On” / “Bang a Gong (Get It On)”
この『HISTORY of UK MUSIC』がスタート地点としている1970年代の初期は、何と言っても、グラムロックが世を席巻しました。そんなグラムロックを語るのには欠かせないのがT. Rex。当時、彼らをThe Beatlesと比較されるほどのスターバンドへと導いたのが、おそらく一度は目にしたことはあるという人が多いであろう、光り輝くギタリストのアートワークのアルバム『Electric Warrior』であり、おそらく一度は耳にしたことあるであろう、40年以上経っても人気な“Get It On”でした。
The Rolling Stones “Brown Sugar”
The Beatlesのように解散して伝説になるバンドもいれば、The Rolling Stonesのように一度も解散せず止まることもなく続けることで伝説になるバンドもいます。1度聴けば耳に残るギターリフでおなじみの“Brown Sugar”は、彼らの長い活動の中でも1970代の1番最初にリリースされたシングルであり、〈Rolling Stones Records〉の記念すべき第1弾シングルでもあります。ファンからの人気も高く、リリース当初から今もなおライヴでは必ずと言っていいほど演奏されている楽曲です。
1973
Roxy Music “Do The Strand”
今もなお現役バリバリで活躍する大ベテランの2人、カリスマヴォーカリストのブライン・フェリーと、アンビエント・ミュージックを起点に電子音楽に革新を与え続けているブライアン・イーノが若かりし頃に在籍していたRoxy Music。メンバーの変動が多く、それによって1期から8期ぐらいまであるそうですが(判断はファンによりけり)、やはり2人の「ブライアン」がいた時が最高に格好良いと思います。そして2人が最後に共作したアルバムからの“Do The Strand”は、心地よい低音ヴォーカルと、はちゃめちゃなシンセメロがハーモニーが見事に合わさった楽曲です。
1975
Queen “Bohemian Rhapsody”
メンバーのブライアン・メイとロジャー・テイラーでさえも「わからない」と言う謎に包まれた内容の歌詞であり、かつ突拍子もない展開を見せる楽曲でありながら、ギネスで英国史上最高のシングルに選出され、イギリスで最も売れた曲としても記録されているのが“Bohemian Rhapsody”。2015年にはリリースから40周年ということで、オフィシャルYoutubeチャンネルにて、楽曲にまつわるドキュメンタリーや数本のライヴ映像が公開されました。
1976
Sex Pistols “Anarchy In The UK”
伝説的なパンクバンド、Sex Pistolsが1976年にリリースしたデビューシングル“Anarchy In The UK”。歌詞中に「片っ端から破壊してやりたい」や「交通を遮断してやる」など、パンクのイメージを作り上げたとも言える一節もありますが、何よりこの曲の歌い出し「I am an anti-christ, I am an anarchist」からは、社会を束縛する(もしくは、し兼ねない)存在に対して切に向き合った上で反抗する、というパンクという姿勢の原点的な思想を感じられます。
1978
The Jam “David Watts”
“David Watts”は、元々はUKが生んだロック界における重要バンドThe Kinksが1967年にリリースした楽曲で、それをThe Jamが、The Kinksからの影響を作品に反映させる形として、1978年リリースの3rdアルバム『All Mad Cons』を制作する際にカバーしたのがこのヴァージョン。The WhoやSmall Facesなど他の先人バンドからの影響も昇華した『All Mad Cons』は、パンクの潮流から登場したThe Jamをモッズ・スタイルの手本的存在へと高め、再評価を推し進めた作品です。若い時のPaul Wellerは本当に格好良いです。
1979
The Clash “London Calling”
伝説でありながらアルバムを1枚しか残していないSex Pistolsとは違い、6枚のアルバムを通じてパンクロックの音楽的な間口を広げて伝説となったのが、The Clash。中でも1979年リリースの『London Calling』は、バンドが従来のパンクから脱し新境地へと到達した金字塔。しかしそのリリース方法は中々パンクで、「12インチ2枚組」とするとレコードの売値が上がってリスナーが買い辛くなるため、バンド自ら「1枚の12インチにオマケ程度でもう1枚付けたい」とレコード会社とずる賢く交渉し、価格を約半分に抑えたそうです。
1980
Joy Division “Heart and Soul”
もうJoy Divisionといえば、黒字に波形が描かれた『Unknown Pleasures』がかなり浸透していますが、アルバムを総合芸術的に考えれば、“Heart and Soul”を収録したラストアルバム『Closer』の方が遥かに美しく感じられます。イタリアはジェノヴァのスタリエーノ墓地にある、アッピアーニ家の墓所の彫像のアートワークは、すでに自ら死を予期していたかのような楽曲群と共に、イアン・カーティスの死=Joy Divisionの終末といった退廃的イメージを見事に作り上げています。
1981
The Police “Spirits In The Material World”
スティングが、戸惑いながらも初めてシンセサイザーを使って作った曲だそうですが、ドラムの手数と、ベース進行とシンセでの和音の弾き方の切り替えだけで、ジャマイカン・スカとロックを行ったり来たりする、なんともThe Policeらしいポスト・パンクな1曲。哲学者のギルバート・ライルが、ルネ・デカルトに反論する際に用いた「機械の中の幽霊」という表現をそのままアルバムタイトル(『Ghost In The Machine』)にしており、これは“Spirits In The Material World”(物質社会の中の魂)というタイトルともリンクしています。
1983
New Order “Blue Monday”
“Blue Monday”というタイトルが示す通り、「憂鬱な月曜日」のことを歌った名曲。この曲を作った彼らは何が憂鬱だったかと言うと、New Orederの前身であるバンド、Joy Divisionのカリスマ的ヴォーカルのイアン・カーティスが初のアメリカ・ツアーを目前に自殺したことでした。しかし、バンドとしてビートからメロディーに至るまで徹底的にエレクトロニックなサウンドを取り入れたこの曲によって、New Orederは一気に知名度とセールス、さらには現在の存在感と影響力を手にすることになりました。
The Smith “The Charming Man”
若い頃のMVを見ても、モリッシーとジョニー・マーが一緒になってこんなに素晴らしいバンドをやっていたなんて未だに信じられません。もしかしたらその幻 の存在がThe Smithsの音楽に魔法をかけているのかもしれないですね。一体どれだけの人がThe Smithsの「再結成ライヴ」なるものを心待ちにしているのかはわかりませんが、どうやら2016年の3月に、The Smithsの承認マーク付き公式Twitterアカウントが登場したそうです。なんだか初期The Smithsのサウンドみたいにドキドキしてきます。
David Bowie “Let’s Dance”
2016年1月に長期のガン闘病の末に亡くなったDavid Bowie。ジャンル問わず多くのアーティストが追悼のコメントをSNSなどで公開したことで、改めて彼が長らく音楽シーンに与えてきた影響と、それを彩った名曲の数々を認識することができました。ボウイといえば、70年代のグラムロックのイメージもありますが、80年代にリリースされた大ヒットシングル“Let’s Dance”(同タイトルのアルバム)も外すことができません。昨今もディスコ/ファンク回帰を牽引するナイル・ロジャースがプロデューサーということもあり、2010年代にもかなり面白く聴くことができます。
1985
Pet Shop Boys “West End Girls”
Pet Shop Boysが世界規模でその名を広めることになった、1885年リリースのセカンドシングル“West End Girls”。単純なニューウェーヴの後進とは異なる、シンセ感たっぷりの電子音によって構築されたファンキーなダンストラックと、出だしのラップっぽいパートは、当時にしてみればやはり新鮮に聴こえたはずで、この2つがヒットした大きな要因とも感じられます。ロンドンにおける東西の格差をリアルに風刺した歌の内容もかなり響いてきます。
1987
U2 “With or Without You”
The White StripesやThe StrokesのようにUKロックっぽいUSのバンドがいるように、USのロックバンドかと一瞬思ってしまうUKのバンドもいて、その代表例がU2。おそらく1987年リリースの5thアルバム『The Joshua Tree』がUSのチャート「Billbord 200」で9週連続1位を記録し、さらにアルバムのリードシングル“With Or Without You”がUKよりもUSでヒットしたことがそのイメージを作り上げている要因になのだと思います。でもプロデューサーはブライアン・イーノで、レコーディングはU2の地元ダブリンで行われたので、曲自体は純UK産です。
1989
The Stone Roses “Waterfall”
The Stone Rosesと言えばセルフタイトルの傑作デビューアルバム。とにかく多彩で、卓越したリズムセクションに耳を奪われますが、ジャクソン・ポロックの作品を模したドッリッピングとポーリングのアートワークとリンクするかの如く混沌としたサイケデリックに引き延ばされたギターサウンドとアルペジオ、レイドバックしたヴォーカルなどなども、同年代のバンドの中では圧倒的な響きをしています。中でも“Waterfall”はメロディーに優しがあり、意識も絶妙にぶっ飛ばすことができます。
1990
Primal Scream “Loaded”
アシッドなお日様マークでお馴染みの超名盤『Screamadelica』に収録された、今もなお多くの人を快感の彼方へ飛ばすアシッドハウスの名曲 “Loaded”。その元はと言えば、1989年リリースの2ndアルバム『Primal Scream』に収録されていた“I'm Losing More Than I'll Ever Have”を、UKの名プロデューサーであるアンドリュー・ウェザオールがリミックスしたことであり、これはロックがダンスミュージックへと転換していく象徴とも言えるでしょう。
1994
Blur “Girls & Boys”
もう本人たちは仲直りしてるのに、もはや定番ネタのように「ギャラガー兄弟か、デーモンか」と議論になるのは、それだけ彼らが優秀なヒットメーカーだったということでしょう。『Park Life』を初のUKアルバムチャート1位に導き、Blurの出世作と称されるまでにしたのは紛れもなくアルバムの初っぱな“Girls & Boys”の軽いノリの良さ! なんですが、歌の内容はこれをクラブで聴いていたであろう90年代初期の若者に対する皮肉になってます。
Everything But The Girl “Missing”
以降現在はそれぞれ別に活動するトレーシー・ソーンとベン・ワットが2000年まで組んでいたユニット、Everything But The Girlは、ネオ・アコースティックやAORの路線でデビューし、高い評価を得てもいますが、セールスとして史上最もヒットしたのはエレクトロニックミュージックを取り入れてからで、その代表曲が“Missing”。今改めてこれを聴くと、2010年代顕著になった、DisclosureやAlunaGerge、Kieszaとかの楽曲は間違いなくUKでヒットする、という流れの源流にいるのはEBTGなのかなと思えてきます。
1995
Oasis “Wonderwall”
サッカーのイングランド代表サポーターが試合前に一体感を高める時や、マンチェスター・シティがリーグ優勝を遂げた時にファンが大合唱したことでも知られる“Wonderwall”。タイトルは、The Beatlesのジョージ・ハリスンが音楽制作を手掛けた同名の映画に由来しているそう。意味は「不思議な壁」……ではなく、「自身を救ってくれる不思議な力を持った存在」のことだそうで、一時は作詞と作曲を手掛けたノエルが当時交際していたメグ・マシューズのことではないかと言われていましたが、離婚後にはその説をきっぱりと否定しています。
1996
Underworld “Born Slippy (Nuxx)”
Underworldの1番の代表曲“Born Slippy”も、後にリイシューした際に同曲を収録した傑作アルバム『second toughest in the infants』も2016年で20周年。アンダーグラウンドのソリッドなテクノが、ドラムンベースやジャングルの力強さを得たようなこの曲を一躍アンセムにした映画『Trainspotting』を知っているかどうか微妙な世代からも支持されるようになって、またさらにダンス・トラックとして魅力を増してたような気がします。
The Prodigy “Breath”
“Breath”のイントロの怪しげなギターリフを思い出すと無性に飛び跳ねたくなってしまうなんて人、いるんじゃないでしょうか? 『チャーリーズ・エンジェル: フルスロットル』のバイクレースのシーンでも使われていた通り、疾走感しかないこのトラックは、The Prodigyの大ヒットアルバム『The Fat of the Land』から先行公開されたシングル。UKシングルチャートではもちろん1位、このMVは1997年の『MTV Video Music Award』にて世界中のヴューアーが選ぶ部門を受賞しました。
Jamiroquai “Virtual Insanity”
20代前半の方はカップヌードルのCMで記憶しているかもしれない、ロンドン発のアシッドジャズ/ファンク・バンドJamiroquaiの代表曲“Virtual Insanity”。いま、「え! Jamiroquaiってバンドなの!?」って思った方もいるかもしれませんが、バンドですよ。歌っているジェイ・ケイのソロ名義ではありません。アシッドジャズはクラブのイメージが強いものでしたが、Jamiroquaiはリースナーのウケとしても、セールスとしてもポップソングへと昇華させました。現在のポップスで言う「ファンキーディスコ・チューン」のベースを作り上げたのも彼らかもしれません。
Spice Girls “Wannabe”
これまでに最も多くのシングルセールスを記録したガールズグループは、1994年にロンドンで結成されたSpice Girlsで、その曲がこの“Wannabe”。メンバーそれぞれが個性的なキャラクターを持つことで、どのメンバーにも当てはまらないファンを無くすという作戦の通り、「あたしの恋人になりたいなら……」「あたしと上手くやっていきたいなら……」という要求が色々並んだ、かなり我が強く押されてる内容のリリックになっています。男性の皆さんは、こんなに押しが強い女性はいかがでしょうか?
1997
Orbital “The Saint”
Underworld、The Chemical Brothers、The Prodigyときたら、もう外せないのがOrbital。Roland TB-303を始めとするARP 2006、YAMAHA DX7といったシンセサイザーを使ったメロディーワークで、アシッド・ハウス・リバイバルとUKテクノのシーンを牽引したことはもちろん、映画のサウンドトラックの制作と提供でも人気を集めました。その中でも“The Saint”は、ハートノル兄弟のメロディーセンスが抜群に発揮されており、今もよく探偵/スパイ的なシーンになるとテレビから流れてくる楽曲のひとつです。
The Verve “Bitter Sweet Symphony”
最近は某人気シェアハウス系リアリティーショーのオープニングテーマにも使われていた、The Verve屈指の名曲。“Bitter Sweet Symphony”というのは、「人生は苦しくもあり楽しくもある交響曲なんだ」という意味であり、その後の歌詞は、デビューから音楽性を高く評価されながらもセールスでは決定的な記録を残すことができなかった、ずっと変われなかった自分たちをネガティヴに歌っているかのような描写が続きます。しかし、なんとそんな葛藤を歌った曲がまさかのロングヒット。真の意味でThe Verveの名刺代わりの曲になってしましました。
1999
The Chemical Brothers “Let Forever Be”
The Beatles中期の名曲“Tomorrow Never Knows”のドラムパートを大胆にサンプリングし、ゲストヴォーカルにはノエル・ギャラガーを迎えた、これぞまさにUKな一曲。また、ロックなソースを ダンスミュージックの形式に落とし込んだスタイルは、The Chemical Brothersの特徴である「デジタルロック」を最もよく象徴しているとも言えます。映像の鬼才、ミシェル・ゴンドリーが手掛けたドラッギーでサイケデリックなMVも必見です。
2001
Radiohead “The National Anthem”
先行のシングルカットやMV制作といった事前プロモーションを一切行わずにリリースをしたにも関わらず、UKやUSなど各国のアルバムチャートで1位を獲得し、その年のグラミー賞の年間最優秀アルバム部門にもノミネートしたRadioheadの4thアルバム『Kid A』。アルバム収録曲“The National Anthem”は今でもライヴで披露されている定番曲で、中毒性のあるベースのリフと、トム・ヨークの最早言葉すらも解体しかけている自由すぎる歌のアレンジで毎度大いに盛り上がります。
2002
The Music “The People”
飾り気のないバンド名、曲名……ですが、フロアを一気に惹きつけるギターリフとヴォーカル、扇動力のあるサビのフレーズは、UKのレイヴ・カルチャーをロックの側から最も体現していたと言えます。The Musicの“The People”はUKの音楽史だけでなく、日本の音楽シーンにも欠かすことができません。大の親日家(というより、フジロッカー?)である彼らは、2002年のアルバムデビューから2011年の解散までにフジロックに6度出演しているだけでなく、プライベートでも訪れているほど。
2003
Muse “Stockholm Syndrome”
Museが現在のスタジアムサイズの壮大なロック世界観の楽曲を意識的に作り始めた時期が、だいたい3rdアルバム『Absolution』の頃からで、同アルバムの軸になっていたのがメタリックな曲調の“Stockholm Syndrome”でした。ハードな演奏でグーっと引き込んでからの、ピアノの美メロを入れて、ドラムの刻みも少し主張を抑えてくるサビ部分は、かなりの開放感と浮遊感があります。ライヴでも未だに披露される定番曲でもあり、アレンジを加えているパフォーマンスが幾つかあって面白ので、ぜひライヴ動画を探してみてください。
The Libertines “Don't Look Back Into The Sun”
ドント・ルック・バック……のアンガーではなく「サン」を歌ったのは、2002年にデビューして以来今もなおロックミュージシャンの憧れの的ともなっているUK直系の伝説的バンド、The Libertines。本曲は2つの名作『Up the Bracket』と『The Libertiens』のどちらにも収録されず、シングルのみで発表されたので、言わずと知れた名曲とも言えるでしょう。あまり分かりやすくは書かれていませんが、おそらくドラッグに溺れていたピート・ドハーティーを叱咤激励する内容の詞なのではと言われています。
2004
Franz Ferdinand “Take Me Out”
1stアルバムに先駆けてリリースされていきなり爆発的にヒットし、未だにFranz Ferdinand史上1位のセールスを記録した楽曲であり、ライヴでは大合唱必至の“Take Me Out”。曲の前後でびっくりするぐらい曲調が変わる不思議な曲ですが、あの変わる瞬間の「ジャッ、ジャッ、ジャッ、ジャッ……」という部分の来るぞ感がどうもクセになってしまいます。でも、「僕を連れ出してよ」って、女性に問いかけているシーンを想像するとなんだか女々しいですよね。最近の感じで言うと草食系。メンバーのキャラクターには合っていそうですけどね。
2005
Arctic Monkeys “I Bet You Look Good on the Dancefloor”
デビューシングルにも関わらずメディアから「Oasis以来の衝撃」と称され、UKチャートでは初登場1位と初週売上4万枚をマークし、若干20歳の田舎モンの青年たちをいきなりスターダムに押し上げることになった1曲。当時すでにチャートを賑わせていたバンドたちは歌わなかったイギリスの若者たちの事細かな生態を、言葉遊びのような速さと言葉並びで綴った歌詞は、いまだに、アレックス・ターナーがいかに優れたソングライターであるかを証明するのに最もわかりやすい例かもしれません。
Gorillaz “Feel Good inc. ”
Blurのデーモン・アルバーンが主導となって2000年代初頭から始動した架空のバンド、Gorillazが最も売ったアルバム『Demon Days』のリードシングルがこの“Feel Good Inc.”。アニメーションのバンドメンバーと、フィーチャリングで楽曲に参加した実物のDe La Soulが共演するMVもかなり話題となりました。バンド同様に、架空の世界をテーマにしたリリックとなっていますが、どう考えても現実世界が見据える末路に対して異議を唱えているようにしか聞こえないです。
2006
Amy Winehouse “Rehab”
2011年に27歳という若さで亡くなった、永遠に語り継がれるべき21世紀の歌姫エイミー・ワインハウスが、マーク・ロンソンをプロデューサーに迎えて作った“Rehab”。アルコールに依存しているエイミーにリハビリを勧めてくる周囲に対して彼女はいつも「No No No」 と断っている、というエピソードをリリックの基にすることを提案したのも、往年のガールズグループ風サウンドに仕上げたのも、マーク・ロンソンの仕事だったそう。そして、後にエイミーの父が明かした、“Rehab”の制作時間がスタジオに入ってから3時間だったという話にも驚きです。
2008
Dizzee Rascal “Dance Wiv Me”
SkeptaやStomzyの登場でここ数年再びブームとなっているUK発のラップ「グライム」の草分け的な存在であり、グライム後進勢のみならずUSのシーンや他のジャンルのアーティストからもリスペクトを受けているのがDizzee Rascal。人気プロデューサーのCalvin Harrisと共作した“Dance Wiv Me”は、UKチャートで初めて1位に輝いたシングル。翌年に発表したArmin Van Heldenとの共作“Bonkers”よりもクールな雰囲気があり、グライム、ヒップホップ・マナーに沿ったトラックとなっています。
Coldplay “Viva La Vida”
過去の3作とは異なる新たな基軸をバンドで見出そうと作られたのが4thアルバム『Viva la Vida or Death and All His Friends』であり、“Viva La Vida”と言うタイトルはメキシコの女性画家/民族芸術フリーダ・カーロの作品にちなんでいる。トラックにストリングスと打楽器を大々的にフィーチャーしているのは、まさに彼らが言う新たな基軸を支える要素であり、完成系はさることながら作っている側も十分に心の開放ができていられるように思います。AppleのCMに起用されていたことで、今でも日本では高い人気を誇っています。
2009
Mumford & Sons “Little Lion Man”
北米大陸に移り住んだケルト系(アイルランド、スコットランド)やアングロサクソン系(イングランド)の民族音楽が元となり、今ではアメリカの主流音楽の 一種となったフォーク・ロックも巡り巡って、2008年に結成されたバンド、Mumford & SunsによってUKに里帰り。デビューシングル“Little Lion Man”は、いきなり2011年グラミー賞の「ベストロックソング」部門にノミネート。惜しくも受賞まではいきませんでしたが、アメリカのフォークうるさがたも認める衝撃のデビューとなりました。
The xx “Islands”
ハウスを基調にしたトラックですが、同じ振りのダンスと同じカメラワークが延々と続くMVが最もダンスミュージック的なループを示唆している “Islands”。デビューアルバム『The xx』のリリース後に12インチシングルとしてカットされ、UntoldやFaltyDL、Nosaj Thingといったプロデューサーがよりダンサブルに仕上げたリミックスも同シングルに収録されました。雨が降るロンドンのストリートをあてもなく彷徨う時にはぴったりのサウンドトラック……なんて賞賛もあります。
Kasabian “Fire”
2011年から2013年までイングランドのサッカーリーグ=プレミアリーグのオフィシャル・テーマとなっていた、Kasabianの3rdアルバム収録楽曲。Kasabianのメンバーは大のサッカー好きで現地スタジアムでよく目撃されているとか。特に現在は、彼らの地元レスターのチーム、レスター・シティ(日本代表の岡崎の所属チーム)が首位独走中ということもあり、居ても立っても居られない状態でしょう。またなんと、現在のレスター・シティの監督が勝利の秘策を「選手たちにKasabianの曲を聴くように言ったから」とも明かしており、躍進にも大きく貢献している様子。
2010
James Blake “Limit To Your Love”
James Blakeが1stアルバム以降にライヴを重ねながら完全にシンガーとして振り切れていくほんの少し前段階的な時期と、彼がポスト・ダブステップ期のプロデューサーに分類されていたかがわかる抜群のベースプロダクションが融合した1曲。……なんですが、実際はFeistのカバー。リリックの一部のみを引用してループ、オーバーダブをしていく作り方は、ある意味「James Blake流のリミックス」というイメージでもあるのかなと考えることもできます。
Adele “Rolling In The Deep”
幼少期にUKの女性シンガー界の先輩Spice Girlsの真似をしながら歌にのめり込んでいったというAdele。グラミー賞で最優秀レコード賞や最優秀楽曲賞などを受賞した“Rolling In The Deep”を収録したアルバム『21』は、米Bilbordアルバムチャートにてマイケル・ジャクソンが保持していた記録を更新する「発売以来39週連続でトップ5位以内」という快挙を成し遂げました。UKの歌姫が、世界の歌姫になった秘密の裏側には、彼女ならではの失恋観と、ポール・エプワースやリック・ルービンといった名だたるプロデューサー陣の融合にあります。
2012
Jake Bugg “Lightning Bolt”
2012年に18歳の時にデビューし、いきなりNoel Gallagher's High Flying BirdsとThe Stone Rosesのライヴでオープニングアクトに抜擢された早熟の天才。ボブ・ディランと比較されたり、いきなり良いチャートポジションを獲得している自身の状況をかなり冷静に見て、「おかしい」と言える辺りも、やはり只者ではありません。写真で見ていると少し幼い印象を受けますが、実際に本物を見てみるとかなり「大人の男」という佇まいで、本人は嫌がるかもそれませんが、カリスマ性をかなり感じられます。
2013
Disclosure “White Noise ft. AlunaGeorge”
ガイとハワードのローレンス兄弟によるユニットのDisclosureが、同世代の2人組AlunaGeorgeとタッグを組んで製作した、モダンなUKガラージ・ハウス。“White Noise”のリリース当時は、まだSam Smithをフィーチャーした“Latch”しか知られた曲がなく、ユニットの素性も多くは明らかになっていなかったにも関わらず、UKシングルチャートで2位を獲得しました。フェスで、サビの「Just noise, white noise.(ただの騒音、ホワイトノイズ)」を何千人、何万人が一斉に叫んでいる光景はなかなか壮観です。
2014
Ed Sheeran “Sing”
元からポップ・フォークを基調にしながらも時折R&Bっぽい歌い回しを見せていたエド・シーランが、ファレル・ウィリアムスをプロデューサーに迎 えた結果、歌い方もリリックもかなりR&B方向に振り切れちゃった1曲。「If you feel you’re falling, Won’t you let me know(もし好きになりそうになったら、教えてくれよ)」なんて、あのハイトーンヴォイスで囁かれたら一瞬で惚れてしまいそうですね。
Sam Smith “Stay With Me”
Disclosureが2012年にリリースしたヒットシングル“Latch”で披露したハイトーンヴォイスで一躍知名度を上げたSam Smith。ここ数年間、常にビッグアワードやメディアから注目を受けてきたものの、弱冠20代前半ながら卓越したテクニックと豊かな叙情性であらゆる期待を上回ってきています。“Stay With Me”では、ハイトーンでアッパーに歌い上げるのに対して、バラードでしっとりしたムードで隙間なくリスナーのハートを覆うこともできる実力を十二分に披露。グラミー賞の主要部門にも輝きました。
2015
Skepta “Shutdown”
Drakeが愛聴を公言し、2015年の『BRIT Awards』ではKanye Westと共にパフォーマンスをした「UKラップ=グライム」のスター、Skepta。“Shutdown”はリリースするや否やすぐにユースのアンセムとなりました。フックで連呼している「Shutdown(シャットダウン)」というのは、「盛り上げる」という意味のスラング。ストリートでも、ショーでも、ファッションウィークでも「俺が出れば即座に盛り上がるぞ」ということを言っています。さすが。「グライムは俺の宗教」と自身の存在を自負する部分もあります。
Stormzy “Shut Up”
WileyやSkeptaといったUKグライムの先人たちから影響を受けていることはもちろん、Frank OceanやLauryn HillといったUSのR&Bアーティストたちからの影響も公言し、実際に自らのMCスタイルに反映させている弱冠22歳のMC、Stormzy。“Shut Up”は、DJ XTCによるグライム・クラシック“Functions On The Low”のビートをジャックしてフリースタイルを乗せた形から生まれた楽曲で、ライヴでは動画のように「Shut up」や「Back up dancer」と合いの手を入れるのがお馴染み。