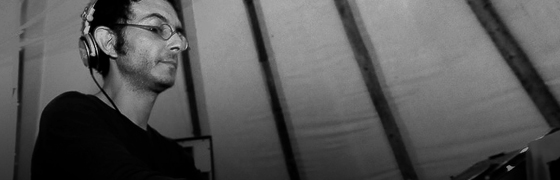3年連続となる野外パーティー・The Labyrinth への出演を通して、日本のシーンでも高い信頼と評価を獲得したDonato Dozzy。"マイクロトランス" と称した彼の広範な音楽性は、前回のインタビュー で彼自身も認めていたとおり、特に自然との調和の中で非常に映えるものであり、初期トランスの楽曲を髣髴とさせるような楽曲から、鋭くトリッピーなテクノ・トラック、また定評あるアンビエントセットでは宇宙の深遠を感じさせる美しい選曲を見せ、野外パーティー好きをはじめ、音楽にはちょっとうるさい、通なパーティーピープルまでも完全に虜にしてしまった感がある。
日本からの止まぬラブコールに答える形で、The Labyrinth から半年も経たずに再来日ギグが決定、いよいよ約2週後に迫るなか、今回は彼の地元イタリアのエレクトロニック・ミュージックWEBマガジン electronique.it とのインタビューを本邦初公開。自国でのインタビューにもかかわらず、The Labyrinth をはじめとした日本のシーンに対して言及していることで、日本のファンが彼によせる想いが決して一方通行ではないことが明らかになるはずだ。
Interview : liquid (electronique.it)
Translation : Shogo Yuzen
Introduction : Yuki Murai (HigherFrequency)
![]()
ローマにある彼の静かなスタジオの中で、我々は Donato Dozzy とインタビューを行った。彼はこの長いインタビューの中で、興味深い話を語ってくれた。
-- やぁ、Donato。まず The Labyrinth でのプレイはどんな感じだったのか聴かせてくれるかな?またこういうイベントで生まれる特別な感覚っていうのはある?
D.D (Donato Dozzy) : ステージに立っている僕という一人の人間と、目の前にいる自分と何も変わらない2,000人の人間の間に起こる相互作用だね。彼らから自分に膨大なエネルギーが注がれていて、自分もそれを彼らに送り返すんだ。ネガティブなバイブスなんて全く無い、真のループだね。みんなが楽しもうとしていて、特別な 『何か』 を自分と一緒に作り出そうとする。そして、自分はリラックスした状態でいられる。それが一番大切なことだね。
感情的な部分で言えば、このパーティーは他とは比べ物にならないよ。環境も、素晴らしい自然に囲まれているしね。The Labyrinth が開催される場所は特別で、音の綺麗さや透明度がものすごいんだ。Funktion One の音響設定にも感謝したいね。入場者は2,000人までに制限されているから、スペースにもゆとりがある。その上、出演するDJはみんなそこで友達になっていくんだ。
もう一つ、このフェスティバルの特徴は、それぞれのショーとショーが本当の意味で繋がるようにしてるんだ。マネジメント側(特にオーガナイザーの Russ)は、各アーティストがきちんと決まった時間帯にプレイできるように気を配ってる。それぞれが最高のパフォーマンスが出来る時間帯っていうのがあるからね。Russ をDJにたとえるなら、僕達パフォーマーはレコードだね。彼は僕が知る中でも最高の 『DJ』 さ!(笑)
-- じゃあ、マネジメントは必要以上に細かいところにまで口を出してきたりもする?
D.D : 必要以上とは思わないよ。ただ、全てがちゃんと計画通りに進むようにしてるだけさ。
-- 参加しているDJたちは、それぞれ近いスタイルを持っているように思うけど、そのせいで他のジャンルに対して排他的な雰囲気にはなったりはしない?
D.D : いや、全くそんなことないよ。たしかにこのイベントは儀式的音楽、サイケデリックな音楽がメインになっているけど、それとは違う、もっと 「ライト」 なリズムの音楽をプレイするようなDJ達もこのイベントに来ているんだ。それぞれの独自の色があってこそ、この音の輪は完成するんだよ。4日間にわたるイベントで同じタイプの音楽が延々とかかり続けてしまったら問題だけど、The Labyrinth の場合はそれぞれのパフォーマンスがいいバランスで組み合わさっているんだ。The Labyrinth はそれぞれのピースが慎重に選ばれて作られる、完璧なジグソーパズルみたいだね。
-- 過去数年間、日本のマーケットは 「特別区域」 として見られていて、プロデューサーの中には日本限定でアルバムをリリースする人もいるよね。日本の人達は他の国に比べて、こういうジャンルの音楽を受け入れる体制が出来ているのかな?他の国の人達と日本人の違いはなんだと思う?
D.D : 世界の音楽ファン達が日本の人達を特に羨む必要はないと思うけど、日本人が他の国の人達と違うところは、彼らは比較的コレクターとしての意識が強いってことだと思う。そして、技術的、音楽的面から音楽をもっと深く追求するところがあるね。今でも日本には Disk Union をはじめとする有力なレコード屋があるし、そこでは他のフォーマットの音源と一緒に、数多くのヴァイナルが取り扱われてるよ。あと、僕が行った "Five G" っていう楽器屋では、確か少なくても5台の909や808が磨きなおされて販売されていたな。他にもたくさんのビンテージの機材やターンテーブルがあったよ。この、音楽に対する関心の深さが、彼らが海外のアーティスト達の活動を追いかけてる理由じゃないかな。彼らは知識が豊富なんだ!過去数年、たくさん日本の人達と話す機会があったんだけど、びっくりするぐらい色んなことを知ってるね。
-- The Labyrinth での君のセットの中から、感情がクライマックスに達したダンス・トラックを3曲、アンビエント・トラックを3曲教えてくれる?
D.D :
おぉ…それじゃあ、まずはアンビエント・トラックについて話そうか。アンビエントのセットではそんな瞬間がいくつかあったね。それを生み出せた理由の一つは、僕が今まで人前でプレイしたことの無いトラックをプレイする勇気が出せたからかな。まず1曲目は、僕がプロデュースした曲、'Rude Boy' だね。僕は普段インストゥルメンタルの曲をメインに作ってるけど、その曲は仲のいい Habib っていう友達にヴォーカルを入れてもらったんだ。
最初、この曲に良い反応が返ってくるかは、正直わからなかった。4年もかけて作った曲だったから、その曲の良し悪しを判断するのも怖かったしね。だけど、プレイする気持ちにさせてくれたのは、Mnml Ssgs の Chris だったね。本当に感謝だよ。彼に数ヶ月前にロンドンでこの曲を聞かせた時、絶対にプレイするべきだって言ってくれたんだ。そしたら、良い反応が返ってきた。間違いなくあれはセットの中でも最も感情の高ぶる瞬間の一つだったね。
2曲目は 'Global Communication - 14:31' だね。この曲については前に話したかな?オーディエンスも僕自身も感動させてくれた曲だよ。そして、3曲目は Mike Parker の 'Arena' だね。近々 Aquaplano からリリースされるよ。プレイしていたとき、空気の密度が上がるのを感じたね。みんな互いに話すのもやめて、6分間音も立てずにトラックの全ての周波数に集中してたよ。
じゃあ、次はダンス・トラックについてだね。一番印象的だった瞬間は Shura on 3B の 'alone' か Motoguzzi Records からリリースされている Cio D'or の 'Pssst!' だね。あの曲は絶妙な周波数で人を落ち着かせるんだ。
だけど、強いベースの曲ではみんな息をのんでたよ!そして、最後は Strive からリリースされている David Alvarado の 'Blue' だね。みんなこの曲には踊り狂ってた!僕が忘れちゃってる部分もあると思うけど、終わり頃が一番盛り上がったところだったと思うよ。
-- セットの最後の曲は?
D.D : 最後にかけたのは、Natural Midi の Scott Grooves がプロデュースした 'Classic 909' だったね。Roland の909で作られたリズム構成に、甘いメロディーが乗った曲なんだ。僕がプレイし終わって、ターンテーブルの電源を落とした瞬間に雨が降り出したんだよ!(笑)
-- 君のセットに参加してると、完全に現実を忘れて、エレクトロニック・ミュージックの最も重要な要素である 「旅(Journey)」 を体験することができるよね。セットはどれぐらい準備をしているの?君はプレイするレコードをどういうやって理解し、そのトラックが素晴らしいセレクションの一部になるにはどれぐらい時間がかかるものなの?
D.D : 僕は自分のセットを組む時に何も準備していないんだ。全部その場の流れで決めていくんだよ。大体いつも『カラー』 を決めるところから始めるんだ。『カラー』 っていうのは、その日のムードに合わせた基本的なテーマだね。そして、始まったら後は成り行きに任せるんだ。だから、僕はセットリストは作らないよ。
僕は自分がプレイするトラックを出来るだけ熟知するようにするんだ。何度も何度も聞いて、そのトラックと僕の間に関係を築き上げるんだ。そして、使われてる楽器や曲が生み出す周波数についてを記憶しておく。そうすることで、曲をマッチさせることが簡単になるんだ。後は、それぞれのレコードが作られた過程のストーリーを掘り下げるのも好きだね。どんな方法で作られたのか、どんな楽器が使われたのか、ジャケットのグラフィックはどんな風に選ばれたのかとかね。フィーリングと、力学的観点の両方からリサーチをするって言えば、分かりやすいかな。
-- 君のセレクションは大きく二つにわけられるよね。一つは催眠的で包み込まれてしまうようなテクノ、そして、もう一つはダウンビートで柔らかな雰囲気を持ったトラック。この二つの異なるスタイルをプレイするとき、どんな感覚なのかな?
D.D : 強くて早い感じのセットでは、僕の体も心も機敏に動いてるんだ。緊迫した感じだね。だからテクノ・セットをプレイしてる時は僕自身もフル・スロットルで、圧迫された感じがするよ。
-- そういう時、オーディエンスには何を求めてる?
D.D : 信頼だね!いつもゼロのところからオーディエンスを掴まなきゃいけない。それが圧迫感になるんだ。でも、自分はベストを尽くさなきゃいけない。そして、オーディエンスから反応が返ってきたら、そこからは簡単なんだ。みんながクレイジーになる。そうしたら、あとは僕も一緒にクレイジーになるだけだからね!
-- 多くのDJはオーディエンスを盛り上げるために曲をスタートのところに戻したりとか、爆発音を使ったりなんかもするけど、君のやり方はもっと巧妙だよね。シンプルなトーン・シフトだけで、彼らをトランス状態にリードしていってる。
D.D : そうだね。僕は一つの大きな盛り上がりよりも、小さなバリエーションがある方が大切だと思うんだ。ベース一本だけでブレイクを作って、次のアルペジオが来るのを期待させる。そういうのが僕のリズムの感じ方なんだよ。もちろんみんながみんながそういうのを感じたいわけじゃないっていうのも理解してるけどね。
アンビエントのセットでは時間が緩やかに流れるから、みんなを無理に躍らせる必要はないんだ。だから、オーディエンスがしっかり自分に耳を傾けてくれていることを理解して、音をマッチさせることで楽しさを作り上げていくんだ。
全くダンスとは正反対な部分だね。テクノ・セットもこういうサウンドは多いけど、アンビエントの場合は踊らせようっていう意図はないのがテクノと違う部分かな。
-- 最高何時間くらいまではプレイしようと思う?
D.D : 一度参加したイベントでそれぞれのDJの持ち時間が20分しか無いことがあった。でもすごくやりがいがあって、楽しかったよ!20分で自分の全てを表現しなきゃいけないからね…
-- それって Combo Cut の時?
D.D : そうだよ。ローマの Metaverso で開催されたんだけどね。それぞれのDJのプレイが終わる度に、20分の休憩を挟むっていうすごくクレイジーなアイデアで進行されたイベントだったんだけど、みんながいいムードになって、短いセットもすごく良かったんだ。結果的にすごく面白かったよ。僕が一番嫌なのは、自分の居場所が無いところに呼ばれることなんだ。他の出演者や全体的な雰囲気と自分が合ってないにも関わらず、1時間プレイしろって言われたりね。ああいうのは大変だよ。そんな時間では何も表現できないからね。
実際に1時間のセットっていうのがすごく難しいのを知ってるから、1時間プレイするように言われると怖いんだ。サイケデリック・ミュージックを扱ってると特にね。オーディエンスは特定の音に順応するから、それがうまくできない時に僕の音楽を誤解されることがあるからさ。だから、過去の経験を考えると、Combo Cut の時もすごく心配だったんだ。実際、僕のサウンドは僕の心配を反映してたと思う。こういう状況だとどうしても、存在感があって、厚みのあるトラックをプレイしがちになるんだ。だから、自分の好きな音楽をかけるのが難しい時はあるね。
オーディエンスがセットに 「取り込まれた」 状態で、3時間目あたりからプレイし始めるような曲が僕は好きなんだ。当たり前だけど、自分の好きなことが出来るからね。だけど、別にそんな状態ってあんまりエキサイティングじゃないよね。
-- 君は多くのDJやプロデューサーが住む、エレクトロニック・ダンス・ミュージックの中心と言われるベルリンにしばらく住んでたよね。ベルリンの街はどんな雰囲気?そして、何故ローマに戻ることにしたの?
D.D : 年だからだね(笑)!ベルリンはまるで天国だよ。この街では、ミュージシャンや自分の将来を探してる人なら、自分と同じような人とたくさん出会うことができる。これは素晴らしいモチベーションにつながるよ。そして、そこで自分が求めていたものを見つけたら、次はそこに留まる理由が必要だよね。僕はベルリンに行く前、イタリアでもそう悪くない生活を送ってたんだ。だけど、イタリアでは自分のアイデンティティーを見つけるのに苦悩したんだよ。だから、自分が共感できる人、新しい友達や新しい文化に出会いたくてベルリンに引っ越したんだ。これがベルリンの素晴らしいところだね。世界中の人がそこに集まってて、みんなが自分の知っていることをシェアしてくれるんだ。
音楽の話をすれば、ベルリンにいる人達の多くはしっかり準備が出来てる。ベルリンでの2年間で得た成長をイタリアで得ることはきっと不可能だっただろうね。僕は最初に Panorama Bar でプレイをし始めて、1週間後にレジデントDJになったんだ。幸いなことに、あのクラブの 「重み」 を知らずにね!オーディエンスとの対話という面ではあそこでの経験は僕にとって最も重要なものだったよ。
たくさんのしっかりとした考えを持ったDJや、良い友達にも会えて、今でも彼らとは連絡を取り合ってるよ。あそこでただ生活したり、呼吸するだけでもためになるんじゃないかな。壮絶な競争があるけど、みんなすごく低姿勢だしね。だけど、ベルリンにはたくさん良い面もあれば、多くの悪い面もあるから、全てを含めて考えてみる必要はあるけどね。世界中のDJがベルリンで暮らそうとしてやって来たから、ベルリンの人達は色んな文化と触れ合ってるんだ。この背景があるから、全体的にみんな成熟していて、他の場所ではタブーとされていることもベルリンでは許されていたり、肯定されていたりするんだ。そして、寛容さやリスペクトという部分で、ベルリンで学べることはたくさんあるよ。どんな人種も受け入れられるしね。『肌の色が濃ければ、濃いほど受け入れられる!』 これは覚えておいたほうがいいよ(笑)。
さらに、ベルリンで生活するのは楽で、物価も高くないんだ。市民や芸術に対しては自治体から社会的サポートもあるしね。だからこそ、アーティストが受け入れられるんだよ。
この寛容さは時に過剰なこともある。月曜日にパーティー出かけたら、パーティーをハシゴし続けて一週間後に帰宅することも出来るような街なんだ。パーティーが、ただの 「次のパーティー」 になってしまう。これが時にアートや創造性にも影響してると思うし、それは決していいことではないよね。
-- じゃあ、ベルリンにいるということは諸刃の剣なんだね?
D.D : そうだね!もし自滅したいなら、ベルリンに墓を掘るべきだよ。(笑)
-- プレイする音楽はどこで購入してるの?丸一日、レコード屋でヴァイナルを掘りながら過ごす楽しみっていうのは今でも感じてる?
D.D : うん。ローマの Remix でも、ベルリンの Hardwax と同じように、全部の棚のレコードを掘ったよ。レコードショップは社交場だし、素晴らしいと思うんだ。自分のような人に出会って、自分の情熱を語り合うことが出来る。そして、お店のオーナーと築き上げる関係もあるよね。そういう環境で育ったから、インターネットでオーダーするのは好きじゃないんだ。ネットを使っていると、イベント以外での人との接点を無くしてしまう。レコードショップではクラブでは会えないような情熱を持った人とも出会うことが出来るんだ。これは本当にいいことだよ。
-- 作品が出るたびに購入するような、絶対にがっかりしないって確信してるアーティストはいる?
D.D : Robert Henke だね。
-- 最近はよりプロデューサーとしての活動が増えてきて、トラックやコラボレーション作を数々生み出してるよね。トラックを作ろうと思ったのはいつ頃だったの?そして、実際に制作はどうやって始めたの?
D.D : トラック制作はキャリアの初期から始めてたんだ。1989年だね。DJを始めた時に自分の好きなレコードがどうやって作られたのかにすごく興味があったんだ。幸運なことに僕には Paolo Micioni 、Pietro Micioni のような師匠がいた。彼らは Gimmick っていう自分達のスタジオも持ってたんだ。彼らはどうやってレコードが作られるのかを僕に教えてくれたんだ。これが80年代の話だっていうのを忘れないでよ?当時使ってたのはアナログの楽器とかだったんだから!
僕のプロデューサーとしての第一歩は、音楽を愛すること、そして、次に自分が学んだことを形にしたいと思ったんだ。その後にはっきりとやりたいことがわかって、楽器を集め始めた。最初に買ったのはサンプラーだったね。当時僕はヒップホップにハマってたから、サンプリングでビートを作りたかったんだ。そして、段々自分のやってることが形になって来た時にコンピューターを使い始めて、全てのピースが一つになったって感じかな。でもこの道のりには15年もかかったよ。
-- この制作の中で一番苦労したことはなんだった?
D.D : 答えは簡単だね!一番難しいのは、自分の頭の中にあるものを音楽に作り変えることだね。僕は自分がトラックを作って満足したことがない。きっとこれからも無いと思うんだ。自分の内部にあるエネルギーを自分の気持ちのままに物質化させる。これがこの仕事の一番難しいところだよ。
-- それは経験を積み重ねることで乗り越えられるものなのかな?
D.D : 運が良ければね。失敗からすごいものが生まれることもあるからね。オーディエンスに向けて出来る限り正直でいることが大切だよ。
-- 「こういう曲にしよう」 と思って、意図的に狙ったような曲を作り出すこともできる?
D.D : まあね。でも本当に技術が無いとできないことだと思うよ。すでにしっかりと 「デザイン」 されたようなトラックをそのまま作り上げるのが得意なアーティストはたくさんいる。でも僕はそれが出来ないんだ。彼らのことをすごいと思うよ。僕はもっと衝動的なんだ。だから僕は波を作って、乗って、何が起こるかを見てみるタイプだね。
ポップミュージックのプロダクションや、大きなレーベルに所属している人達は締め切りがあったりするのも理解してるよ。ポップのプロダクションや大きなレーベルが求めてるものはまた違うんだ。音楽を意識的に作る技術が必要なんだよ。
-- 君のスタジオには Roland のTB-303が二つあるよね?一つは Devil Fish が付いてるやつ。エレクトロニック・ミュージックファンの間ではすごく定着してる機材だけど、この楽器を選んだのは何故なの?
D.D : 僕は1970年に生まれて、1988年にアシッドが出てきた時には18歳だったんだ。あれは衝撃だったね。その頃に303のサウンドはもう知ってただけど、まさかあんな音が作れると思ってなかったんだ。僕はあのサウンドが好きだった。魅了されてたね。若い頃に Heaven 17's の 'Let me go' を始めて聞いた時は 「うわ!この音楽は他の惑星から来たんじゃないか!?」 って思ったぐらいだった。303のベースラインを上手くプログラミングして作られた Imagination の 'Just an illustion' も衝撃だったね。
僕の世代がこの機材のすごさを本当の意味で知ったのは、これが 「正しくない」 使い方をされ始めてからだね。あの頃はみんなこの小さな機材がエレクトロニック・ミュージックの方向を大きく変えると思ってたよ。実際にはそれから何年も立ってから購入したんだ。303を使いこなすにはしっかりと準備が必要だと思ったからね。ソフトウェアをうまく作ってああいう音を再現することはできるけど、実際にそれを使って音を作るっていうのは当時の時代を使って糸を紡ぐってことだからね。
-- Devil Fish についてもっと聞かせてもらっていいかな?
D.D : Mike Parker がこの機材について話してたのに魅了されたんだ。だから、もう一台303を購入して Devil Fish にしたんだよ。これを生み出したオーストラリアの Robin Whittle に感謝だね。2年間リリースしてなかったデモを作り溜めてた時、ちょうどこの楽器と巡り合ったんだ。Devil Fish はクラシックなベースラインを全く違うものに変えてミステリアスなものに仕上げてくれる。この機材には完璧な音が揃ってるから、これだけを使って、ほぼ完成に近いトラックを作ることができるよ。それにヤバイベースも使えるしね!
-- 君が手がけた作品以外で303の利点を最大限にまで使ってると思う曲は何かな?そして、自分自身が手がけたもので一番うまく303を使ったと思うのは?
D.D : 曲を絞り込むためにまずは僕の作品の話からしようか。(少し考えて)OK、この曲だね。Giorgio Gigli と一緒に作った 'Real Love'。この曲では僕達が求めてた音を忠実に機材から引き出すことが出来たんだ。その音って言うのはリズムとしても使えるベースラインで、かつ色んな周波数を持った音だったんだけどね。出来る限り音の少ないトラックを作ろうと思ったんだ。そして、Devil Fish のお陰でそれを実現できたんだよ!
他のアーティストが使ったベースラインに関していえば、さっき話した Heaven 17 の 'Let me go'、そして Armando の '151!' 、それか Phuture の 'Acid Tracks' だね。僕はこの機材の柔軟性がすごく好きなんだ。ハウスのトラックにしか使えないわけじゃないからね。Massive Attack の 'Protection' にも使われているし、K&D Sessions の名盤、Kruder & Dorfmeister がリミックスした Bone Thugs'n Harmony の '1st of the month' にも使われてるよ。
-- 君のサウンドは自分自身を完璧に反映してるといえるぐらい、完成されたものになっていると思う?
D.D : 僕は自分の音楽に対して、はっきりとした結論を出すことはできないんだ。だから、そんなことは言えないね。色々なプロジェクトを始めたのに、やる気がなくなって手付かずになってるものもあるしね。これはよくあるんだ。僕のハードディスクを見れば、そういう未完成のトラックがたくさん入ってるよ。全部その時の気分次第なんだろうね。時に僕は短い時間で楽しみながらトラックを完成させることもあれば、燃え上がらない火花で終わってしまうことも多いしね。
-- ソフトウェアだけを使ってトラックを作ろうとは思う?
D.D : 多分、ひとつのチャレンジとしては悪くないね。僕はアナログの楽器を使って自分のトラックを実現することにあまりにも慣れてしまってるから…。だけど、僕は別に 『アナログ原理主義者』 ではないから、デジタル楽器を排除するようなことはしたくないんだ。だから時々ソフトウェアを立ち上げて、そういう音を探すこともあるよ。ああいう音もすごく面白いし、僕は魅力を感じてるからね。僕はちゃんとアイデアの裏づけがあるなら、どんな手法も取り入れたいと思ってるよ。
-- ちゃんとしたプロデューサーになるためにかかる時間は最低でもどれぐらい必要だと思う?
D.D : それは主観的なことだと思うな。自分のアイデアをしっかりと形に出来るようになるまでにどれぐらい時間がかかるか、だよね。ただがむしゃらに、色んなものを作り続ける人っていうのは僕はあんまり信用しないようにしてる。それはある意味自己管理が出来てないってことだからね。プロデューサーっていうのは、きちんと自分に制限をかけられて、自分のことをしっかりわかってなければだめだと思うんだ。そして、正直に、そして一貫性を持ってオーディエンスに接することかな。それが本当の意味でのプロデューサーになる最終的な一歩だと思うよ。
-- この 『プロデューサー』 っていう言葉は9割方間違った形で使われていると思う。君みたいにスタジオを持ったプロデューサーとこうやって話を出来る機会もあんまりないよ。この意見には色んな反論もあると思うけど、僕達は10年前みたいに限られた人達だけが音楽を作っていて、いい音楽が聴けるような時代に戻った方がいいと思うこともある。今現状にある、音楽の大衆化に関してはどう思ってる?
D.D : 日々、大量の音楽がウェブ上に流し込まれることによって、手の付けられない混乱が起きてると思うんだ。これは良くも悪くもあると思う。昔とは比べ物にならないぐらい選択股が増えているのはいいことだよね。90年代の初頭には Future Sound of London みたいな、あまり一般的ではない楽器が揃ったスタジオを所有して、音楽を制作しているアーティスト達がいた。そして、彼らは自分達のやっていることを愛していたよね。彼らの曲を一曲聴けば、そこには実に見えるもの以上のものがあるんだ。つまり彼らの経験や情熱、そして、長年培ってきた彼らの技術を感じることができる。もちろん、そういう技術をコンピューターを使って再現できないとは言わないよ。だけど、でもこの新しい 「手軽さ」 が、たくさんの音楽を生み出すことを可能にした。だから良いものを見つけることが難しくなってるんだよ。
もちろんテクノロジーは、現在の作り手と消費者の両方を助けていると思う。例えば、昔なら楽器を探すのにわざわざ飛行機に乗って、ロンドンやアメリカまで行かなきゃいけなかったのに今では簡単になったしね。でも最終的には、今でもバランスは保たれてると思うよ。
-- この大混乱の中で、君が現在の音楽シーンから自分自身を隔離して、他の音楽を見下すっていうことはありえるのかな?実は僕ら electronique.it が会ったアーティストや、または僕が個人的にインタビューを読んだアーティストの中には、誇らしげに 「自分はエレクトロニック・ミュージックのシーンには属していない」 っていう人もいるんだ。時には初期のアーティストやレコード、歴史も知らないっていうアーティストもいるぐらいだよ。
D.D : これも主観的なものじゃないかな。僕も、完全に自己中心主義で、自分で作った音楽しか知らない人達を知ってるよ。だけど、彼らの作る音楽もすごく良いんだ。けど、一方で出来るだけ多くの情報をかき集めてるアーティストも知ってる。シーンの大ファンだね。彼らの場合は、自分達をシーンの中にカテゴライズしてるんだろうね。
-- ところで、今はどんなプロジェクトを進めてるの?君がアルバムを出すって言ってる人もいるけど、どうなのかな?
D.D : 僕はアルバムは絶対作らないよ!作れるわけがない!(笑)いや、それは冗談だけどね。まだ音楽業界に望みを持っていた頃は、アルバムを作ることも考えてたんだ。だけど、その後に業界全体の暴落があって、レコードの売上も下がって、物事の管理も悪くなった。丁度その頃にイタリアに戻って、全てを考え直したんだ。その時からアルバムを作るっていうアイデアの現実味は薄れたかな。もし今アルバムを作るなら、妥協もなく、完全に自由なものを作りたいね。ただ僕の思った通りのことがやりたい。でも不思議なことに今こそそういうものを作るべきタイミングなんだよ。だって今レコードを買う人間っていうのはそういうのが好きだからね。アルバムを作るならそういうものしか作らないよ。
あと最近、カセットテープでアンビエント・ミュージックをリリースしないかって言われたんだ。すごく刺激的だと思ったね。限定された枚数で手作りのアートワークのものを出すっていう考えは昔から好きなんだ。今は、アルバムを作るならリスニング主体のものに興味があるね。
-- サウンドトラックを作りたいと思ったことは?
D.D : うん、あるよ。すごく興味がある。誰かの映像作品にインスパイアされるのを待ってるんだ!
-- 他に進めているプロジェクトはある?
D.D : Aquaplano だね。今現在僕が関わってるもので一番気に入ってるよ。友達の Manuel Fogliata (a.k.a.Nuel) と一緒に作ってるんだけどね。お互い、技術面から人間性までを知り尽くしてる。Aquaplano は本当の意味でのプロジェクトだよ。期日をちゃんと守って、意味のあるもの、つまり音楽だけにフォーカスしたものなんだ。これから3作目を作るんだよ。でも Aquaplano を語る上で一番大切なのは、これは僕らの友情のストーリーだってことだね。そこに嘘も偽りも無いんだよ。
-- 君のレコードコレクションについて教えてもらえるかな。人生においてそれはどれぐらい意味を持ってた?そして、テクノ以外のレコードはどれぐらい持ってるの?
D.D : 僕のコレクションには全ジャンルのレコードが揃ってるよ。一枚一枚が僕の人生において大事な一歩だね。ロック、レゲエ、ヒップホップ、ダブ、ドラムンベース、クラシック、フォーク、ソノリゼーション、イタリア音楽…色んなものが揃ってるよ。
-- イタリアのアーティストで好きなのは?
D.D : Paolo Conte, Franco Battiato, PFM, De Andre が一番好きだね。次に Gino Paoli, Mina, Rino Gaetano、その他たくさんだね。
-- ディスコの影響は受けてる?
D.D : すごくね。ディスコには魅了されてたよ。Moroder の 'The Chase' は子供の頃に聞いて、驚いたね。ベースラインから、バスドラム、メロディーまで今の僕のスタイルに影響を与えてるよ。まだかけたことはないけど、今の僕のセットの中に組み込んでも全然大丈夫な曲だね。
-- そろそろこのインタビューも終わりなんだけど、人生で一番のレコードはなんだと思う?たった一枚だけ。一番君が聞いたレコードを知りたいんだ。
D.D : The Who の "Tommy" だね。
-- それは何故?
D.D : あのレコードはサイケデリックな時代のものでしょ。あのレコードには時代を超えるようなトラックがいくつか入ってるんだ。とてもアシッドなテーマで、素晴らしいアレンジやリズムが施されていて、すごい表現力を持ってる。僕が思うに、あれはその世代を本当によく表現していると思う。今のサイケデリック・テクノはあの音楽から生まれたんだと思うよ。当時、The Who のギグにいくって言うのは、そうだな、Jeff Mills のギグにいくぐらいの衝撃があったはずさ。いつもあのレコードを聴いてるよ。
End of the interview
--------
【Donato Dozzy Japan Tour Info】
2010年 1月22日(金)- PROVO presents "SYNAPSE" 1st Flight, 2djs Long Set @ PRECIOUS HALL (Sapporo)
2010年 1月27日(水)- SALOON × combine DAIKANYAMA FREE SESSION 「LOST」 @ Combine Daikanyama (Tokyo)
2010年 1月29日(金)- MOKMAL SOUND PRESENTS "420TOUR×ART" @ UNIT (Tokyo)
2010年 1月30日(土)- @ CLUB MAGO (Nagoya)
関連記事
INTERVIEW : Donato Dozzy vol.1 (2009/06)
PARTY REPORT : THE LABYRINTH 2009 @ 苗場グリーンランド, 新潟 (2009/09/19〜22)
PARTY REPORT : THE LABYRINTH 2007 @ KAWABA CAMP SITE, GUNMA (2007/09/14〜17)
関連リンク